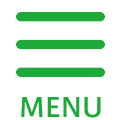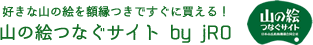羽根田治の安全登山通信|続・今夏の反省 ヨーロッパ・アルプスで得た教訓
- ホーム
- > 自救力
- > 羽根田治の安全登山通信
前回のコラムで、今年の夏山シーズン中に危うく富士山で低体温症になりかけた話を書いた。そもそもシーズン初めに富士山に登ろうと思ったのは、自 分の体力をチェックするとともに、8月に予定していたヨーロッパアルプスの取材に備え、事前に3000m以上の高度を体験しておきたかったからだ。
その取材の話が出たのは6月中旬ごろのことで、当初の予定では山岳ガイドの取材を兼ねてマッターホルンに登ろうという話になっていた。最初は「自分にマッ ターホルンは無理だろう」と思っていたのだが、「大丈夫。登れますよ」と人からおだてられ、インターネットなどで登頂の記録などを見ているうちに、「う〜 ん、なんとかなるかなあ」なんて思うようになってしまったのだから、身の程知らずというのは恐ろしい。
ところが、富士山に登ったはいいが、その後、取材の計画が宙ぶらりん状態になってしまった。自費での取材ゆえの費用の問題、ほかの仕事との兼ね合い、同行する編集者の仕事のスケジュールなどから、「ちょっと無理そうだね」というムードになってきたのだ。
そうした問題が早い時点でクリアされれば、出発予定の8月中旬までの約1ヶ月間、しっかりトレーニングを積み、直前にもう一度、富士山に登って体をつくっ ておくつもりだったのだが、「中止になるかも」と思うとモチベーションも上がらない(ちょっと言い訳がましいけど)。結局、8月上旬まで海抜0mの沖縄の 離島に滞在し、トレーニングもまったくしないで連日飲んだくれるという毎日を送っていた。
それが一転し、8月に入って急遽、取材の決行が決まったのだが、時すでに遅し。体も気持ちも準備不足の状態で、とりあえず装備だけそろえてスイス に向かったのである。まず最初はグリンデルワルトに滞在し、ユングフラウヨッホ展望台へ。ここは日本で言えば立山黒部アルペンルートの室堂みたいなところ で、登山電車を乗り継いでいけば、標高3454mのヨーロッパアルプスの一角に立つことができる。お手軽に体を高度に慣れさせるにはうってつけの場所だ が、一気に高度を上げたので、さすがに頭がふらふらした。
その翌日は、マッターホルンの足慣らしとして、メンヒ(4107m)の西稜を登ること になった。それまで富士山より高い山には登ったことがなく、クライミングだってここ10年以上していないのに、いきなり4000m越えのバリエーション ルート。地元のガイドが我々に付いてくれるとはいえ、不安は大きかった。
当日は雲ひとつない素晴らしい天気に恵まれ、9時40分に3人でアンザ イレンしてユングフラウヨッホ展望台を出発した。小さなクレバスが口を開ける雪原を登って取り付きに立ち、いよいよ登攀開始。いざ岩に取り付いてみると、 岩登りの感覚がすぐに蘇ってきた。恐怖感はほとんどない。わくわくした高揚感が沸き上がってきて、「岩登りってこんなに楽しかったっけ。日本に帰ったら、 またクライミングを再開するか」とさえ思った。
だが、それも最初のうちだけだった。2時間以上が経過したころから徐々にスタミナが切れてきたの だ。いちばん戸惑ったのは、休憩をとらずに登り続けたこと。これまで山に登るときには、1時間前後歩いて5〜20分程度の休憩をとるというのが当たり前 だったが、このとき初めて休憩をとったのは2時間半後のことだった。
行動再開後は明らかに登るペースが落ち、立ち止まって息を整える回数が増え てきた。ガイドからは「深く大きく息を吸って」「立ち止まっちゃダメ。ゆっくりでいいから歩き続けて」と檄が飛ぶが、息が苦しく、どうしても途中で立ち止 まってしまう。これは高度の影響というより、明らかにトレーニング不足によるものだと思う。
上部の雪稜に至ったところでアイゼンを装着し、滑落 したら一巻の終わりという斜面をビビりながらもどうにか通過した。あとは雪の斜面をひと登りするだけなのだが、この時点ですっかり体力を消耗してしまい、 数歩歩いてはしばらく立ち止まって息を整えることの繰り返し。深く大きな呼吸をすることができず、過呼吸のような早く浅い呼吸になり、一歩がなかなか前に 出せない。見かねたガイドが私のザックを持ってくれ、午後2時35分、ようやくメンヒの山頂に立つことができた。
山頂で15分ほど休んでいるう ちに少しは体力が回復し、ノーマルルートをたどっての下山にとりかかる。ノーマルルートとはいえ、両側がすっぱり切れ落ちた雪稜と岩場が交互に現れ、一瞬 たりとも気は抜けない。「自分がつまずいたらガイドと編集者を道連れにしてしまうなあ。いくらなんでも、それは申し訳ないよなあ」などと思いながら下って いくうちに、再び息が上がってきた。雪稜ではスリップに、岩場ではアイゼンの引っ掛けに神経をすり減らし、肉体的疲労に精神的な疲労も重なって、またもバ テバテになってしまった。
立ち止まって息を整えようにも、登山鉄道の最終便を逃すわけにはいかないので、ゆっくり休むこともできない。リードを 付けたよぼよぼの老犬さながら、半ばガイドに引っ張られるようにして足を一歩一歩前に出すのみ。遅々とした歩みに、ガイドと編集者はかなりイライラしたこ とだろう。下の岩場まで来たところで、ガイドがまたも私のザックを持ってくれた。「いや、自分で担ぐよ」とは言ってはみたが、最終電車の時間が迫ってお り、少しでもスピードを上げなければならないので仕方がなかった。
やっとのことで雪原に降り立ち、ほぼ平坦な雪道を急いでなんとか最終電車には間に合ったが、自分にとっては熱中症にかかった西表島縦断と並ぶ、これまでで最もツラい登山となった。
標高4000mちょいのメンヒでさえ、この体たらくである。マッターホルンはこれより標高が約400mも高くなるうえ、標高差約1200mのバリエーショ ンルートを1日で往復しなければならず、クライミング技術に加え、なによりスピードが要求されるという。メンヒでこれだけバテバテになった私が、どう考え たって登れるわけがない。それをはっきりと悟り、マッターホルンには登らないことにしたのは言うまでもない(登山ベースとなるヘルンリヒュッテまでは行っ てみたけど、やっぱり無理だと思った)。
反省点はたくさんある。なんといってもいちばんダメダメだったのは、体力不足である。もっと早く計画を確定させ、少なくとも1ヶ月間でもちゃんとトレーニングをしていたら、ちょっとは違った結果になっていたかもしれない。
だが、それ以前の問題として、趣味や仕事で山に登る機会が多い以上、日ごろからトレーニングをして体力をつけておくべきでしょ、という話だ。山で最後にも のを言うのは、やっぱり体力だと思う。いくら技術や経験や知識があったとしても、それを役立たせることができるのは、体力があってこそ。なにかアクシデン トが発生したときでも、体力に余裕がなければ適切な対処もできない。体力はあり余るに越したことはなく、今さらながらその重要性を身に染みて実感した次第 である。
また、体力が高まれば、付随してスピードもアップする。スピードがアップして迅速に行動できるようになれば、それだけ安全性も高まる。 逆にスピードが遅いと、さまざまなリスクが生じやすくなってくる。現地のガイドが顧客にスピードを要求するのはそのためだ。これまで山に登るときにはあま りスピードを意識したことはなく、せいぜい標準コースタイムぐらいで歩ければいいだろうと思う程度だった。今後はもっとスピードを意識して山を歩くように し、2〜3時間休まずに歩き続けるトレーニングとかも取り入れてみようかと考えている。
それからもうひとつ教訓となったのは技術の問題だ。岩登 りの技術に関してはなんとかなったが、雪上技術は正直、危うかった。とくに恐怖を覚えたのは、急斜面のトラバース、両側が切れ落ちた雪稜歩き、アイゼンを 装着しての岩稜歩き。そういう経験を最後にしたのはもうずいぶん昔のことだったので、緊張で体がガチガチになってしまった。恐怖は体を硬直させ、それに よってリスクはより増大する。その恐怖を解消してくれるのが、技術と経験だ。このところ冬山といえばテレマークスキーばかりだったが、もっといろいろなシ チュエーションでの雪山経験を積む必要があることを痛感した。
そう考えてみると、マッターホルンに登るなんてとんでもない話で、ガイドに引っ張 り上げられるようにしてなんとか登れたメンヒですら、ほんとうは自分の実力に見合わない山・コースだったと思う。いくらガイド登山だったとはいえ、一歩間 違えば取り返しのつかないことになっていたはずだ。自分の身の丈に合わない山には、たとえガイド登山であっても行くべきではないということも、今回の経験 を通して得た教訓のひとつである。
余談だが、マッターホルンの話題ついでにもうひとこと。先日マッターホルンに登頂したイモトアヤコさんがヘリコプターで下山したことについて、野 口健氏が「テレビはそこまでやるんだね」 と発言して話題になったが、それを聞いて思い出したのが、数年前に取材したある山岳救助隊員の言葉だ。
彼は、まるでタクシーを呼ぶかのようにヘリでの救助を要請する登山者に対して静かな怒りをひととおり述べたあと、「でもね」と言ってこう続けた。
「山に登ったあと、自力で下りるのが嫌なら、極端な話、下山する手段としてヘリをお願いしたっていいと思うんですよ。もちろん、ちゃんと自分で代金を払ってね」
彼の言ったことには一理ある。山に登るときに、ロープウェーやケーブルカーやリフトやバスなどを使って行けるところまで行くことに対しては、誰もなにも言 わない。バックカントリースキーの世界にも、ヘリスキーやキャットスキーというものがある。マッターホルンに登るにしても、ほとんどの人はツエルマットか ら標高2583mのシュヴァルツゼーまではゴンドラを利用している。「だったら下山するときにヘリを使うのだって同じことだろう」と言われれば、たしかに そのとおりだ。
国内では山での遭難事故が増え続けており、その多くは下山時に起きているという現実がある。ならば事故防止という意味でも、下山するときにヘリを利用するのもありだね、という考え方がこれから支持されるようになるかもしれない。
たとえば北アルプスの主な山小屋には、荷揚げのためのヘリポートがたいてい備わっている。そのヘリポートを利用して、夏山シーズン中の午後に2便、下山の ためのヘリを飛ばすというビジネスが成り立つ可能性は充分にありえる(航空法上の問題はあるかもしれないが)。それはそれで、時代とともに多様化する山登 りのあり方のひとつなのだろう。
だが一方で、イモトさんがヘリコプターで下山したというのを聞いて違和感を覚えたのもまた事実だ。アコンカグア に挑んだときのテレビもちょっと見たが、彼女の体力と根性は並大抵ではなく、その心は最後まで折れることがなかった。だからこそ、今回も自力で下山してほ しかった。そう思ったのは、やはり「山登りというのは、自分の足で登って自分の足で降りてくるもの」という野口健氏の意見に共感するからだ。「じゃあ、お 前が剱岳に登るときにはアルペンルートを利用するなよ」言われると困ってしまうのだが。
そうした線引きをどこでするのかは、誰かが基準を設けて人に押し付けるものではなく、結局のところ、個々がそれぞれ持つ価値観に従うしかないのだろう。