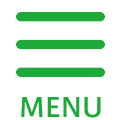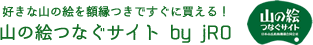オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|怪異と山岳遭難の意外な共通点。正しく恐れることが危機を回避する
〝怖い話〟を信じる? 信じない?
この世には霊感の強い人と、そうでない人がいる。
私はまったくないほうらしく、これまでに怪奇現象を体験をしたこともなければ、その手の恐ろしげなものを見たこともない。
では、霊的なものを信じないのかというと、そういうわけでもなく、存在していてもおかしくはないと思っている。存在を信じていながらも、「自分には霊感がないから」という安心感がどこかにあるのだろう、この世にあらざるものの話は決して嫌いではない。ていうか、むしろ好きだ。映像や書物の〝ほんとうにあった怖い話〟的なものには昔から心惹かれていたし、山小屋の主や山岳救助隊員が〝身の毛もよだつ恐ろしい体験談〟を語りはじめれば、思わず固唾を飲んで聞き入ってしまう。
拝み屋で怪談作家の郷内心瞳さん
で、最近のマイブームとなっているのが、郷内心瞳さんの怪談実話シリーズだ。郷内さんは、宮城の山間部で拝み屋を営みながら、作家としても活動されている方である。
拝み屋というのは、本人曰く、〈相談客から依頼された、先祖供養や加持祈祷を執り行うのが拝み屋の主たる仕事だが、時には悪霊払いや憑き物落としといった物々しい業務を手掛けることもある〉とのこと。その本業を通した実体験や、依頼客が語った話などを怪談実話として書籍で発表されているのだが、それらが最凶に恐ろしく、読みはじめたら止まらなくなってしまった。
一般的に、「怪談」「祈祷」「悪霊払い」「憑き物落とし」といった言葉からは、ある種のいかがわしさが感じられるものだが、郷内さんの作品にはほとんどそれがない。自ら素性を詳細に明らかにしていることで、読者は「もとより実話に基づいてる」という前提に立って、物語を読み進んでいけるからだろうか。
実際、顔出しもしている本人へのインタビュー記事を読むと、自身の拝み屋という仕事や特異な体験を、第三者的な一歩引いた眼で見ているように感じられる。インタビュアーも、「お話をうかがっていると、郷内さんはすごく常識的、中立的ですよね」と、その印象を記事のなかで述べている。逆にいえば、常識的・中立的な視点だからこそ、作品の怖さや凶々しさがいっそう引き立っているのだと思う。
ほんとうに怖くて危険なことは
その郷内さんの『拝み屋備忘録 怪談腹切り仏』(竹書房文庫)という本を、先日、手に取って読みはじめた。本は、「前書き」にあたる「『怖い』を知らないという怖さ」と題された一文から始められていた。それを読んで、いきなり衝撃を受けた。
以下は、そこからの一部抜粋である。
〈実のところ、怖いものを知らないということこそが、本当に怖いことだと私は思う〉
〈過度に恐れない気持ちは大切なのだけれど、畏怖や畏敬の念を失して軽々しく接してよいものでもない〉
〈何が怖くて何が怖くないか。それを判別できる力がなければ、思わぬ時に思わぬ形で、とんでもない危険に身を晒す事態にもなりかねない〉
さて、私は実際に起きた山岳遭難事故を取材・検証し、そこから得られる教訓を登山者に伝えることを生業のひとつとしている。その根底には、同様の遭難事故を防止するのに多少なりでも役に立つはずだとの思いがある。
そして雑誌や書籍、あるいは講演などを通して遭難事故防止について語るとき、私はある言葉を何度も繰り返し紹介している。クライミングインストラクターで山岳ガイドの菊地敏之さんが、その著書『最新クライミング技術』(東京新聞出版局)のなかで書いた、次の一節である。
〈結局のところ「危険」が最も危険なのは、その危険を察知できないことにある。問題なのは、なにが危険なのかわからない、危険をシミュレーションできない、危険なことを危険なことだと考えられない、ということなのだ〉
郷内さんの言葉は、怖いものに対して、あるいは恐怖という感情自体に対して、鈍感になってきている昨今の人々に向けられている。一方の菊地さんの言葉は、山に潜んでいる危険について知ろうとしない登山者に対して向けられている。
しかし、対象と言葉は違えど、言っていることは同じである。つまりは、「怖さ」や「危険」に対して無知・鈍感であるのは、とても怖くて危険なことなのだ、と。
情報過多が現実感の喪失を招く?
郷内さんは、人々が怖いものに対して鈍感になってきている要因について、こう考察する。
〈ネット環境やSNSの発達により、今や携帯端末を所持しているだけで、望む情報の大半は手に入り、貴重な知識や感動までをも容易に手にすることができる。
ただ、その手軽さゆえにそれを自分の一部とし、体験する時の現実感も希薄となって、実感が伴わなくなっている面もあるのではないか〉
これは登山についても当てはまる。かつては、登ろうとする山の情報を得ようとしたら、ガイドブックか地図を見るしか手段はなかった。あるいは現地の山小屋に電話で問い合わせるか。
しかし今は、SNSやブログを通して、膨大な数の個人の山行記録を誰でも容易に見ることができる。その信憑性はさておくとして、行こうとしている山・コースの記録をいくつか見れば、概要どころか詳細までもがほぼ把握できてしまう。
さらにはYouTubeに代表される動画投稿サイトにも、登山系YouTuberが入山から下山までを懇切丁寧にレポートするコースガイド的な動画がごまんとある。動画ではコースの状況、危険箇所、山頂からの展望、山小屋やテントサイトの様子、下山後の温泉などが臨場感たっぷりに紹介されているので、見るだけで自分がその山に登ったような気分になってしまう。
動画によるこうした疑似体験は、動画を撮影したYouTuberと自分を同一化するという現象をもたらす。はたしてそれが、いいことなのか悪いことなのか。
文字や写真では伝えきれなかった情報を伝えられるという点で、山やコースのより詳細な状況がわかるので、登山者にとってメリットは少なくない。だがその一方で、本来、山に潜んでいるリスクを、現実のものとしてのリスクと捉えられなくなってしまうという負の側面もあるのではないだろうか。郷内さんがいうところの、「現実感が希薄になることによる弊害」である。
リスクに対してあまりに無防備であることに端を発する最近の遭難事故ーー自分たちの力量に見合わない計画、軽装すぎる装備、登山のルール・原則を守らない行動などによる遭難事故ーーを見聞きするにつけ、ついついそんなことを考えてしまう。
想像力の欠如が窮地を招く
それにしても不思議なのは、どうして先を見通せないのか、ということだ。
「昼過ぎから登りはじめたら、山頂に着く前に真っ暗になるな」
「こんなスニーカーで雪山に登ったら、絶対滑落するよな」
といったように、現状を顧みてちょっとでも想像力を働かせれば、にっちもさっちもいかない状況に追い込まれるであろうことは、容易に予想できるだろうに、と思うのだが。
それも動画の影響なのかどうかはわからない。ただ、動画によって提供される情報は、前振りから過程を経て結論に至るまでのすべてを、目に見えるものとして視聴者に届けられる。視る者はそれをすんなり受け入れて消費するだけだ。想像力の欠如は、そんなところからももたらされるのかもしれない。
〈人は何をすれば自ら怪異を呼びこび(注:原文ママ)、どんなことに警戒すれば怪異を回避できるのか〉
この郷内さんの言葉の「怪異」を「危険」に置き換えれば、そのまま山の教訓となる。
「怪異」にしろ「山の危険」にしろ、対処の仕方を誤れば、生死に関わる最悪の状況を招いてしまう。
登山者に求められるのは、現実感を以ってして想像力を働かせ、考えて行動することではないだろうか。
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)がある。