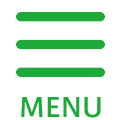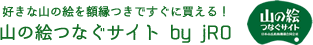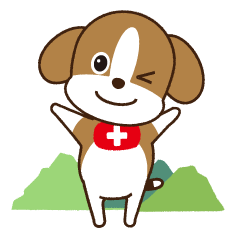オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|トークイベントに寄せられた質問への回答
さる10月25日、26日の2日間、京王高尾線高尾山口駅前で「高尾山の市 “野市”」というマーケットイベントが開催され、その2日目に「あなたはもう遭難している?! 高尾で遭難?」というお題でトークイベントを行なう予定だった。しかし、悪天候のため、残念ながら26日のイベントはすべて中止となってしまった。事前に参加を申し込んでいただいていた方には申し訳ないが、天気ばかりはどうしようもない。もしまた機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
さて、トークイベントでは、参加予定の方から事前に寄せられた質問に答えるつもりでいたが、その機会もなくなってしまったので、せっかくだからこの場を借りてお答えすることにします。なお、スペースの都合上、すべての質問にお答えできないことをご勘弁ください。
Q1.年齢を重ねて行くなかでの山行で、とくに気をつけていかなければならないことは?
昨今の遭難事故の多くは、自分の体力や技量に見合っていない山に登ろうとすることで起きている。報道を見るかぎり、その傾向は高齢になるほど顕著なようで、自分の実力を過信している人がかなり多いように思われる。よく言われていることであるが、「自分が登りたい山=登れる山」ではない。大事なのは、自分の体力・技術レベルを正当に評価して、実力にあった山・コースを選び、無理のない計画を立てて山に臨むことだ。
そのためには、ガイドブックの標準コースタイムの何割程度の時間で歩けるかというのがひとつの目安となる。また、毎年1回は必ず登る山を決めて、所要時間や疲労度などから現在の体力レベルを判断するという方法もある。そのほか、長野・富山・岐阜・山梨など10県と2山系で採用されている「山のグレーディング」も、自分の体力・技術レベルを知るうえでの参考になるので、活用するといいだろう。
なお、「登山は冒険だから」と、自分の実力以上の山にチャレンジしようとする人もいるかもしれない。それを否定する気はないが、敗退したときのことまでを想定して、複数のエスケープルートを設定する、引き返すターニングポイントを決めておく、予備日をとっておくなど、より入念にリスクマネジメントを行なう必要がある。「ダメだったら救助を要請すればいい」というのでは、最初から挑む資格はない。
もう一点、中高年層が注意しなければならないのは疾病である。加齢に伴い生活習慣病のリスクは高くなるし、身体のあちこちにガタがきていたり、持病を抱えていたりする人も少なくない。近年は病気による遭難事故も増加傾向にあるし、登山中に心疾患や脳疾患などを発症して突然死する事例も散見される。自分の身体になんらかの問題がある人はもちろん、たとえ自覚症状がなくとも、ある程度の年齢に差し掛かったら、信頼できるかかりつけ医に相談しながら登山を続けることをお勧めする。
Q2.北八ヶ岳を登山中、霧に包まれ道がわからなくなった。晴れるまでじっとしているのが安全といわれているが、不安が先に立ってウロウロしてしまった。不安解消方法があったら教えてほしい。
霧やガスなどで視界がきかなくなり、進む方向がわからなくなってしまったときに、やみくもに動き回るとルートを外れてしまったり、危険な場所に入り込んでしまったりする。また、方向感覚を失うことで、無意識的に同じ場所をぐるぐる周回するリングワンデルングに陥り、無駄に体力を消耗してしまうこともある。
たしかにその場でじっとしているのは不安だが、長時間に渡って視界が閉ざされることはほとんどなく、しばらくすれば霧やガスが上がったり、一時的に視界が開けたりする。そのときに進む方向を見定めて行動すればいい。なかなか視界が開けそうもない場合は、ツエルトやエマージェンシーシートをかぶって晴れるのを待とう。体を冷やさないのに役立つだけでなく、不安を軽減させる効果もある。
地図アプリを携行しているのなら、視界がなくとも現在地がわかるので、地図の表示に従って正しいルートをたどることも可能だ。地図とコンパスで方向を定めて進む方法もあるが、高度なテクニックなので、使い方を熟知している必要がある。

ガスにまかれて視界がきかなくなったら、無理せず晴れるのを待とう
Q3.遭難したり、遭難に近い経験をされたことはあるか?
2005年のゴールデンウィーク、友人と2人で西表島を縦断中に熱中症にかかり、行動不能に陥ったことがある(拙著『山岳遭難の教訓』に体験記事を収録している)。このときは行動を開始直後から体調不良を自覚していたが、途中から疲労困憊状態となり、しまいには全身の筋肉が攣って、激痛にのたうちまわるハメに。結局、この日は予定していた幕営地までたどりつけずにビバークし、症状が若干緩和した翌日、ボロ雑巾のような状態でなんとか下山した。当時はなにが原因なのかわからなかったが、後日、ドクターに尋ねてみると、「それは重度の熱中症だ」と指摘された。
また、専門学生時代、6月にひとりで西黒尾根から谷川岳に登ったとき、頂上付近の残雪で滑落してしまい、「終わったな」と思った経験もある。このときはピッケルもアイゼンも携行しておらず、雪の上を滑りはじめた身体は徐々にスピードが増すばかりだったが、斜度が落ちてきたところで靴の踵を雪面に蹴り込んで、ようやく止まることができた。このときはほんとうに生きた心地がしなかった。
そのほか、岩場でクライミングをしていたときに、終了点に着いて掴んだ木の枝が折れて、あわや転落しそうになったり、狭い登山道で石につまずいて斜面に転げ落ちそうになったり、バックカントリースキー中に足首を捻挫してターンができなくなったりするなど、ヒヤリハットの経験は数えきれないほどある。幸いいずれも大事に至らなかったのは、ただ運がよかっただけだと思っている。
Q4.山で遭難している人、あるいはアクシデントに見舞われている人に出くわしたことはあるか? 現場のリアルタイムな話を聞いてみたい。
私自身がそのような状況に遭遇した経験はない。ただ、長野県警や富山県警などは、YouTubeに公式チャンネルを開設して、遭難救助の動画などを随時アップしている。これらを見ると、遭難事故現場のリアルな状況がひしひしと伝わってくる。救助活動がどのように行なわれるのか、そしてその活動がいかに危険を伴うものなのかもよくわかるので、ぜひチェックしてみることをお勧めする。
余談だが、ある遭難事故について関係者にインタビューしたときに、彼が中学・高校時代に所属していた山岳部では、山で遭難者に行き合ったときのことを想定して、どう対応するかについて、さまざまなシミュレーションを繰り返し行なったという話を聞いた。その後の救助活動をスムーズに行なう上では、そのようなノウハウも必要不可欠となるはずなので、セルフレスキューの技術のひとつとして普及することに期待したい。
Q5.遭難したときに生還するための気持ちの持ち方を知りたい。
遭難しはじめたときに、あるいは遭難してしまったときに、多くの人は「家族に心配をかけたくない」「なんとしてでも今日中に下山したい」「ニュース沙汰になってしまうのは絶対に避けたい」といった、「遭難をなかったことにしたい」という心理が強く働くようだ。その結果、自分が置かれている状況を冷静に分析できず、「とにかくこの窮地を脱しなければ」と焦って行動し、いっそうドロ沼にハマっていくパターンがかなり多いということを、これまでの取材を通して感じている。
その一方で、遭難した当初からすでに達観していたような人もいた。60代の男性は単独で奥秩父の山に登って道に迷い、9日後に自力下山したのだが、話を伺って感心したのは、遭難している間、ほぼ冷静さを保ち続けていたことだった。さすがに遭難初日は、家族のことなど心配になることがいろいろあって、焦りもしたという。しかし、「考えてもどうにもなるものではない」と開き直ったことで、「何日かかってもかまわないから無事に下山できればいい」と頭を切り替えられた。以降、彼は「ジイさんなんだからぼちぼちいこうよ」「いつかは道に出るよ」と自分に言い聞かせながら行動を続け、生還を果たすことができたのだった。
また、北アルプスの後立山連峰を単独で縦走中、下山を目前にして滑落し、行動不能に陥ってしまった70代男性の場合は、その場で救助を待つことを早々に決断した。ケガは擦り傷程度で済み、現場のすぐ上には登山道が通っているはずだったが、周囲の地形から自力で脱出するのは無理だと判断し、「ジタバタしてもしょうがない。運を天に任せよう」と待機を決めた。結局、男性が救助されたのは8日後のことだったが、ずっと救助を待ち続けていられたのは、入山時に登山届を出していたからで、それが「きっと捜し出してくれるはずだ」と信じられる根拠になっていたという。
いずれのケースにしても、「無理してでも下山しなければ」という強迫観念にとらわれることなく、アセらずに長期戦を覚悟し、いくら時間がかかろうと、とにかく無事に生きて帰るのを最優先したことが、生還につながったのだと思う。その気持ちを持ち続けるうえでは、登山届を提出するとともにそれを家族らと共有すること、ココヘリの会員になっていること、登山アプリの位置情報の共有機能を使用していること、衛星通信サービスを利用していることなどが、大きな支えになるのはいうまでもない。
Q6.クマに遭遇した時の対応方法を教えてほしい。
これについては、基本的には前々回と前回の当コラムで触れたとおり。ただ、前回のコラムには、クマに襲われたときの最終手段として、「防御姿勢をとった場合のエビデンスがないので、応戦するか防御姿勢をとるか、どちらがいいのかはわからない」と書いた。しかしその後、秋田大大学院などの研究班が、「防御姿勢をとったほうが重症化を回避できる」などとする調査結果を、2025年7月発行の『臨床整形外科』60巻7号に発表していたことがわかった。これによると、2023年度にクマに攻撃されて負傷した秋田県内の70人(平均年齢70.0歳)のうち、地面にうつ伏せになって首のうしろで手を組む防御姿勢をとった7人全員が、重症化を免れていた。防御姿勢をとらなかった人たちのうち23人は、指や手足の切断、多発外傷、全身麻酔による手術を要する傷を負うなどの重症を負ったという。この調査結果は、防御姿勢の有効性を示す初めてのエビデンスではないかと思う。ちなみに受傷部位は、顔面が55.7%と最も多く、続いて手や腕が54.3%、頭部が44.3%だった。
前回のコラムにも書いたが、攻撃を仕掛けてくるクマに対し、人は本能的にとっさに応戦してしまうケースが多いようだ。防御姿勢をとるというのは、無抵抗でやられるがままになることを意味し、かなり勇気がいる行動だと思う。しかし、自己防衛のためのクマの攻撃は短時間で終わることが多く、結果的に防衛姿勢をとった人が軽傷で済んでいることが、この調査で明らかになったわけだ。クマの攻撃に対し、重傷化を回避する有効な手段として、今後は防衛姿勢をとることが奨励されていくだろう。

クマに襲われたときには、防御姿勢をとって身体の急所をガードする
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』『あなたはもう遭難している』(山と渓谷社)がある。