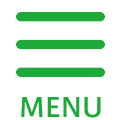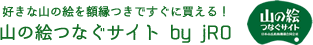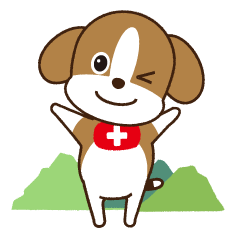オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|クマの出没や人身被害が多発する今、クマ対策の定説を再考する

登山口に掲示されたクマの目撃情報
一般登山道やキャンプ場にまで出没するクマ
前回の当コラムでは、今年の8月14日に北海道知床の羅臼岳で起きた、ヒグマによる登山者の人身事故について触れた。その後の報道によると、羅臼岳ではこの夏、登山者とクマとの至近距離での遭遇が相次いでいたため、8月12日に注意喚起を促す看板を登山口に設置、13日には環境省と斜里町、知床財団の職員が登山道のパトロールを行なったという。しかし、クマが確認されなかったため、登山道を閉鎖するまでには至らなかったが、その翌日に事故が起きてしまった。
環境省や北海道、斜里町、知床財団などで構成される「知床ヒグマ対策連絡会議」は、9月11日に記者会見を開いて事故の経緯を発表し、事故後から実施している登山道の閉鎖は、事故の検証結果と再発防止対策がまとまる2026年以降にまでずれ込む見通しを示した。
知床だけではなく、今年はクマと登山者の遭遇が各地で多発している。北アルプスの鹿島槍ヶ岳では8月15日、山頂にツキノワグマの親子が現れ、食事を摂っていた登山者が驚いて逃げ出した隙に、弁当を食べられてしまうという事案が発生した。山頂には約20人の登山者がいたにもかかわらず、クマは20メートルほどの距離まで近づいてきたとのこと。冷池山荘のホームページによると、種池山荘〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳の主稜線周辺では、同一個体と見られるクマの親子がたびたび目撃されており、冷池山荘のテントサイトにまで姿を現したこともあったという。
北アルプスでは8月19日の夕刻、薬師岳と太郎兵衛平の間にある薬師峠キャンプ場にもツキノワグマが出没し、登山者のテント一張と食料を持ち去っていくという被害が出た。当時、キャンプ場には約50張のテントがあったが、これを受けてテント泊の登山者は太郎平小屋や薬師岳山荘に避難したという。今シーズンは周辺の稜線上でクマが頻繁に目撃されており、キャンプ場を管理する県は、利用者の安全確保が難しいとして今季の営業を取りやめる決定をした。
ちなみに薬師岳の登山口にある折立キャンプ場では、2023年8月にクマが連日出没し、登山者が背後から襲われてかすり傷を負ったり、テントやザックが荒らされるなどの被害が連続したため、しばらくキャンプ場が閉鎖されていた。また、立山室堂でも、みくりが池でツキノワグマが泳ぐ姿が確認されるなど、今夏はクマの目撃情報が多発したため、一部登山道を閉鎖したりクマの出没に対応する常駐体制を敷くなどの措置がとられた。
そのほか、今年の5月以降は、東北の八幡平、滋賀県の金糞岳、奈良県の大峰山系、南アルプスの小日影山や易老岳などで、登山者がクマに襲われて負傷する事故が起きている。
近くなりすぎた人とクマとの〝距離〟
元来、クマは臆病な動物であり、通常は人間を恐れていて、いち早く人間の気配を察すればクマのほうからその場を離れていく。しかし、至近距離でばったり遭遇してしまうと、自分の身や子グマを守るために必死で襲いかかってくる。クマによる人身事故といえば、かつてはそのようなパターンがほとんどだった。ところが近年は、人を恐れない、人と遭遇しても逃げ出さないクマの存在が、各地で多数報告されている。なぜこのようなことが起きているのか。考えられるのは、やはり人間とクマとの〝距離〟が近くなりすぎたことだろう。
かつては、野山の森林地帯を生活圏とするクマと、人里で生活を営む人が適切に棲み分けをしていて、その間にある里山が両者の緩衝地帯となっていた。しかし、過疎化や高齢化などで里山が荒廃し、今はクマが里山にまで生息圏を広げるようになっている。おまけにコロナ禍で行動が制限された数年間は、登山者らがほとんど山に入らなかったため、その間にクマが登山者の活動域にまでテリトリーを広げたという指摘もある。また、食料となるドングリなどの堅果類が不作の年には、クマは餌を求めて人里へ、ときには市街地にまで下りてくる。さらに、野山や観光地でゴミの放置やポイ捨てをする、野生動物に餌を与える、SNSでの「いいね」稼ぎのために近づいて写真や動画を撮るなど、ルールやマナーを守れない人たちも目立つようになった。
これらの要因によって、クマと人との距離が近くなりすぎた結果、〝人慣れしたクマ〟が出現するようになって今に至るというわけだ。
クマ鈴は効果なし? クマ撃退スプレーがあれば安全?
では、クマが人を恐れることなく登山道を悠々と闊歩し、登山者が持つ食料に興味を示し、ときにキャンプ場にまで出没する現在、これまで信じられてきた対応策はもう通用しないのだろうか。
たしかにクマの生態や性質は変わってきているのかもしれない。しかし、それは大きく変化した環境の周辺に棲むクマに限定した話であって、全国に生息するクマがすべて人馴れてしているとは思えない。生き物の本能がそう簡単に変わるはずはないので、ほとんどのクマは人を恐れていると思う。
今よく言われているのは、「クマ鈴は効果がない。逆にクマを引きつけてしまう」という説だが、そもそもクマ鈴は自然界にない音を発することによって人間の存在を知らしめ、その場から立ち去らせるためのアイテムである。今年の9月24日付の毎日新聞に掲載された「クマ鈴は有効だが『無敵』ではない 遭遇防ぐために知るべき生態は?」という記事のなかで、知床財団のスタッフは「クマ鈴は有効なアイテムです」と断言している。ただし、風向きや地形(沢の近くなど)によっては音が通りにくくなることもあるので、「無敵のお守りではない」とも付け加える。「鈴の音がクマを引きつける」という説については、クマの生態に詳しい東京農業大学教授の山﨑晃司氏が「音や人に慣れたクマが鈴の音を聞いて立ち去らないことはあっても、音を頼りに人に近づいてくることは現状では考えにくい」と述べている。記事では、遭遇を避けるために手を叩いたりラジオを流したりするなど、意識的に大きな音を出すことを奨励している。爆竹音や犬の吠え声などを大音量で流せるクマ避けホーンも有効かもしれない。
クマと遭遇したシーンでは、距離がある程度離れている場合は、慌てて逃げ出すのはNGで、あとずさりしながら距離を広げていくというのが定説だ。しかし、平坦な林道ならまだしも、整地されていない登山道でそれをやると十中八九転んでしまう。おそらくその瞬間にクマは襲いかかってくる。ベターなのは、ヘタに動かず、フリーズして静かに様子を伺うことだろう。そうしながら、いつでもクマ撃退スプレーを発射できるように準備しておくといい。
そのクマ撃退スプレーだが、ネット上にはクマが退散していく動画が何本もアップされており、それらを見る限り、効果はあるように思える。しかし一方で、真偽のほどはわからないが、「捕食目的のクマにスプレーを噴射しても怯まない」という話を聞いたことがある。8月の羅臼岳での事故が起こる2日前には、登山道上で接近してきたクマにスプレーを噴射したにも関わらず、およそ5分間に渡って付きまとわれたというニアミスも起きている。突進してくるクマを射程距離まで引きつけて、目と鼻を狙って的確に噴射するのも、そう簡単なことではないだろう。スプレーにしろクマ鈴にしろ、「持っていれば絶対安心」というものではなく、「クマによる人身事故のリスクを低めるためのもの」ぐらいに考えておくのがよさそうだ。
さて、クマ撃退スプレーを持っていない場合の最後の手段として紹介されているのが、ザックを背負ったままうつ伏せになり、首のうしろで手を組む「防御姿勢」である。自己防衛のためのクマの攻撃は通常1分以内で終わるといわれており、この体勢をとって急所を守れば、致命傷はまぬがれるというわけだ。だが、攻撃してくるクマに対して、無抵抗でやられるがままでいるのは難しく、これまで私が取材してきたなかでは、本能的に応戦した人がほとんどだった。その結果、重傷を負った人もいれば、運よく軽傷で済んだ人もいた。
防御姿勢をとった場合のエビデンスがないので、どちらがいいのかはわからない。「応戦するとクマは余計に逆上するからやるべきではない」という説のほうが一般的のようだが、応戦してクマを撃退したケースもたしかにある。前回でも触れた2023年10月の大千軒岳でのケースでは、ナイフで応戦したことによって命拾いをしているし、クマ対策としてナタを携行する人もいる。もう15年ほど前に取材した、北アルプス150山を単独日帰りで踏破した男性は、山でのクマ対策として手製の槍(たしか鉄パイプの先端を尖らせたもの)を持ち歩いていた。内心、「クマ対策のために物騒な武器を携行するのはいかがなものか」と思ったものだが、人馴れしたクマの存在が問題視されるようになっている今は、それもありなのかもしれない。登山者が武装しなければならない未来というのはあまり想像したくはないが……。
結局のところ、クマに遭遇する状況は千差万別であり、クマの性格や個性も〝十匹十色〟だろうから、クマの対処法に正解はないと思う。なにを信じてどれを採用するかは、人それぞれだ。
ただ、近年表面化している人間とクマとの軋轢は、元をたどれば、クマが生活していた環境の変化による食料をめぐる問題だと思う。この問題には自然の中に人間が持ち込む食べ物も大きく関わっている。人とクマとの距離がこれ以上近くなりすぎないように、そして人馴れするクマを生み出さないように、せめて我々は食料とゴミの管理ぐらいは徹底するようにしたいものである。
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』『あなたはもう遭難している』(山と渓谷社)がある。