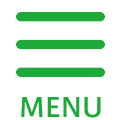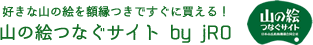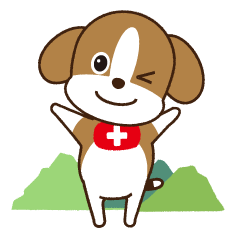オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|知床・羅臼岳で起きたヒグマによる衝撃的な人身事故

北海道に生息するヒグマ
事故はクマの捕食行動だったのか
さる8月14日、北海道知床の羅臼岳で、男性登山者がヒグマに襲われて亡くなるというショッキングな事故が起きた。
この日の午前5時ごろ、20代の男性2人パーティが斜里町の岩尾別登山口から入山し、羅臼岳に登頂した。その下山途中の午前11時ごろ、先行する26歳男性のおよそ200メートル後方を歩いていた友人が、自分の名前を叫ぶ先行男性の大声が聞こえてきたため先を急いだところ、男性がヒグマと格闘しているのを目撃した。友人は勇気を振り絞って素手でクマに殴りかかり、男性から引き剥がそうとしたが、びくともしなかったという。男性は両足の太ももから多量に出血しながらも懸命に抵抗していたが、登山道脇の藪の中に引きずり込まれていってしまった。
現場は「オホーツク展望」に近い標高約550メートル地点で、友人は事故発生直後に110番通報して事故を報告。警察は新たな登山者が入山しないように羅臼岳の登山道を閉鎖するとともに、すでに入山していた約70人の登山者を順次ヘリコプターで山麓に搬送した。
翌15日、警察や地元ハンターらが早朝から男性の捜索を再開し、午後1時ごろ、事故現場付近で親グマ1頭と子グマ2頭を銃で捕殺した。消息不明となっていた男性は、現場近くで遺体となって発見された。
この不幸な事故は、一般登山道上で登山者が突然クマに襲われ、なすすべなく山中に引きずり込まれてしまい、それがいっしょに登山をしていた仲間の目の前で起きたという点で、あまりに衝撃的だった。それゆえ多数のメディアがこぞって大きく取り上げ、ネット上にもさまざまな見解、考察、憶測などが飛び交ったわけだが、報道された事故発生時の状況からしてまず疑問に思ったのは、「クマは捕食目的で人を襲ったのか」ということだった。
これまでにもヒグマによる食害事故があったことは、広く知られるところである。古くは吉村昭の小越『羆嵐』のモデルになった1915年12月の「三毛別ヒグマ事件」、1970年7月に日高山脈のカムイエクウチカウシ山で、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会パーティがヒグマに付きまとわれて3人が命を落とした事故。
最近では2023年5月、幌加内町朱鞠内の朱鞠内湖の湖岸で、釣りをしていた男性が行方不明となり、のちに激しく損傷した遺体が発見されるという事故があった。現場付近をうろついていたヒグマを駆除してDNA鑑定などを行なった結果、このクマが男性を襲って食害したことが明らかになった。
また、同年10月には、北海道福島町の大千軒岳を登山していた30〜40代の男性3人が、休憩中にヒグマに襲撃されて軽傷を負う事故も起きている。襲われた際に男性のひとりが応戦し、ナイフで喉元を刺すと、クマはナイフが刺さったまま逃げていった。この事故を受けて現場へ向かった警察は、登山口に放置されていた車を見つけ、山中を捜索したところ、車の持ち主である22歳の男子大学生の遺体が発見された。遺体のそばではクマの死骸も見つかり、このクマが3人の男性を襲って反撃されたクマと同一個体であること、胃の内容物から大学生がこのクマに襲われたことが判明した。
これらを含めたクマによる食害事故の被害者は、下腹部や臀部、下肢を食べられていることが多いという。野生動物家の木村盛武氏は、著書『慟哭の谷 北海道三毛別・史上最悪のヒグマ襲撃事件』(文春文庫)のなかで、捕食目的のクマに襲われた遺体の特徴として、「食害が最もひどいのは、顔面、下腹部、肛門周辺である」と述べている。羅臼岳での被害者も、顔と上半身に複数の傷があったほか、性別がわからないほど下半身の損傷が激しかったそうだ。
メディアの報道によると、事故が起こる直近の8月10日、岩尾別コースの登山道上で、2頭の子グマを連れた親子グマが目撃されている。3頭は登山者の存在を意に介さなかったそうで、その外見から今回の事故のクマと同一個体である可能性が高いと推測されている。
さらに同12日にも、やはり岩尾別コースの登山道上で成獣のヒグマが登山者に目撃された。登山者はクマが接近してきたため、クマスプレーを噴射したが、その後も約5分間にわたってクマに付きまとわれた。このクマについても、「事故の個体と特徴が似ていた」との情報が寄せられたという。
また、知床国立公園内や周辺道路では、観光客が車の中から野生のヒグマにスナック菓子を与えたり、弁当などの残飯を捨てる行為も確認されている。こうしたことから、知床に生息する野生のヒグマは、人間は食料を与えてくれるもの(もしくは所持しているもの)と学び、〝人馴れ〟して人間を恐れなくなっているのではないか。そして人とクマとの〝距離〟が非常に短くなったことにくわえ、なにかのきっかけでクマの行動がエスカレートした結果が、今回の事故なのではないか。というのがメディアや識者らの見方だった。
加害グマの特徴と事故発生時の状況
しかし、8月21日、知床財団が発表した調査速報(9月10日時点では9月1日発表の第2報が最新版)は、そうした見方をちょっと変えるものだった。
事故を起こしたクマについて、報告書は「2014年(出生年)から知床国立公園で毎年のように目撃されてきた」「国立公園内の道路沿線など人目につく場所で繰り返し目撃されており、今年に入り当該親子グマと思われるヒグマの目撃情報が30件以上寄せられていた」「『人を避けない。人に出会ってもすぐに逃走しない。』といった行動段階1から1プラスに該当する行動が度々確認されており、これらの行動を抑止するため、捕獲個体への追い払い対応(忌避学習付け)を繰り返し行ってきた経過がある」と説明する。ただし、人を避けないヒグマ、人に出会ってもすぐに逃走しないヒグマは知床半島全域で多数確認されていて、この個体の際立った特徴とはいえないそうだ。
注目したいのは、事故現場と事故発生時の状況についての記述である。
・事故現場は、登山道が岩峰の南側を巻くように付けられていて、山頂方面から下ってくると、岩峰の陰となるため先の見通しが悪い。
・岩峰付近は、夏にヒグマのエサとなるアリが恒常的に発生し、ヒグマの出没が多発する場所として知られている。事故翌日も多量のアリの発生が確認された。
・被害者は同行者から約200メートル離れて先行、単独で走って移動していた可能性が高い。登山全体の行程から類推してもかなり早いペースで下山していたと思われる(トレイルランニングだったのかどうかは不明)。
つまり、被害男性は同行者と離れてかなり早いペースで下山しており、見通しの悪い箇所に差し掛かったところで、アリを摂食していたヒグマの親子に遭遇した可能性が高い。スピードが出ていた状態で、出会い頭的に至近距離でばったり遭遇したとすれば、お互いびっくりするのは当然のことであり、回避する余裕などとてもなく、親グマは子供を守るために本能的に男性に襲いかかったものと思われる。
これはこのケースに限ったことではなく、トレイルランニングやスピードハイキングでは、登山に比べるとクマとの遭遇を回避しにくく、遭遇してしまったときには襲われるリスクが高いものと考えたほうがいい。実際、トレイルランニング中(=早いペースで移動中)のクマによる人身事故は、これまでにも何件か報告されている。たとえば2016年5月の奥秩父・両神山、2023年8月の京都・比叡山、2024年6月の長野県木島平村など。2008年9月に世界的なクライマー・山野井泰史氏が、自宅近くの奥多摩の山中でクマに襲われて重傷を負ったのも、トレーニングでジョギング中のことだった。
防御のための攻撃が捕食に切り替わった?
ただ、クマが自身や子供を守るための攻撃は、通常1分以内の短時間で終わるとされており、これらの事故でも命までは落とさずに済んでいる(環境省のデータによると、2008年度〜2023年度のクマによる人身事故の死亡率は、ツキノワグマが1.5%、ヒグマは25%)。しかし、今回の羅臼岳での事故では、単に防御のための攻撃にはとどまっていない。被害者を藪のなかに引きずり込んでいったこと、ハンターらが翌日クマを発見したときにも被害者を咥えて引きずっていたことから、食害していたことは明らかだろう。
とはいえ、クマに「捕食しよう」という意図が最初からあったかどうかは疑問だ。前述したとおり、たしかに〝人馴れ〟していたかもしれないが、地元では〝岩尾別の母さん〟と呼ばれている、問題行動のない大人しい母グマだったという報道もあった。これはあくまで私の推測だが、唐突に人間と遭遇して驚いた母グマが、子供を守るための攻撃をしているうちに、捕食のスイッチが入ってしまったのではないだろうか。
そんなことがありえるのかと思われるかもしれないが、東京農業大学教授で日本におけるクマ研究の第一人者である山﨑晃司氏は、『人を襲うクマ 遭遇事例とその生態』(山と溪谷社)のなかで、クマによる捕食目的の攻撃について、次のように記している。
〈悩ましいのは、防御目的の攻撃が対象とした人を死亡に至らせ、その後そのクマが遺体を食物として認識して食害する場合と、最初から食物として攻撃を行なう場合の判別が難しい点である〉
そうだとすれば、このケースでも、防御目的の攻撃がどこかの時点で捕食目的に切り替わったとしても、おかしくはない気がする。もちろん、最初から捕食嗜好があった可能性も否定できないが。
いずれにしても、この事故の詳細については、9月10日現在、不明な点も多く、専門機関による調査の続報や、識者による分析・検証を待ちたいと思う。
また、当コラムの次号では、クマの生態や性質の変化が指摘されるなかで、登山者はどう対応すればいいのかについて考えてみたい。

ツキノワグマは本州と四国に生息する
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』『あなたはもう遭難している』(山と渓谷社)がある。