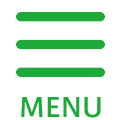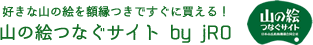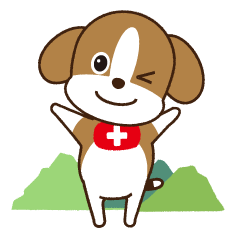オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|バックカントリー遭難が多発した年末年始。富士山ではトンデモ登山者の滑落事故も

バックカントリーはゲレンデスキーの延長ではない。専門的なノウハウと雪山&滑走装備が必要だ
警察庁発表の発生状況は?
さる1月17日、警察庁はこの年末年始(12月29日〜1月3日)における山岳遭難事故の発生状況を公表した。それによると、発生件数は前年の同時期より22件多い52件、遭難者数も同35人増の67人で、いずれも統計が残る2003年以降で最多となった。遭難者の内訳は死者4人、行方不明者3人、負傷者は17人、無事救出が43人。遭難者のうち登山届を出してしたのはわずか7人で、大半が未提出だったことが判明した。事故要因は、道迷いが24人で最も多く、滑落10人、転倒8人と続いた。発生件数の都道府県別では、最多の兵庫6件に続き、長野5件、北海道4件という順になった。
この数字から伺える顕著な傾向というのはあまりなさそうだが、遭難者数も発生件数も過去最多だったということは、冬山登山者の総数が増えているからなのだろうか。都道府県別で兵庫県での事故が最も多かったのは、昨今の〝低山ブーム〟を反映してのことなのか。遭難者の登山届の提出率が悪い(登山届を出さない人のほうが遭難しやすい)のは冬山に限ったことではないと思うが、季節によって登山届の提出率が異なるのかどうか。そんなことがちょっと気に掛かった。
やはり目立ったバックカントリーでの事故
さて、次に報道された個々の事例を見てみると、とくに目立っていたのがバックカントリーでの遭難事故である。次に主な事例の概要を挙げておく。
まず12月30日、野沢温泉スキー場の管理区域外の国有林でバックカントリーをしていた50歳男性が、雪に埋まって動けなくなり、いっしょに滑っていた仲間から警察に救助要請が入った。これを受けて警察や地元の山岳遭難救助隊員が現場に向かい、通報から約4時間後、体の一部が見えている男性を掘り出して山麓に搬送したが、死亡が確認された。事故当時の野沢温泉村の積雪は124㎝で、平年の1.9倍だったという。
ニセコアンヌプリでも1月3日、中国籍の45歳男性がバックカントリースキー中に雪に埋まって動けなくなる事故が発生したが、男性は救助要請後にどうにか自力で雪の中から脱出。目立ったケガもなく、ことなきを得ている。
吾妻連峰では12月30日の午後4時40分ごろ、西大巓付近でひとりでバックカントリーをしていた52歳の男性から、「片方のスキー板をなくし、身動きが取れなくなった」と110番通報があった。警察と消防は、男性のスマートフォンの位置情報をもとに翌31日朝から捜索を開始したものの、年が明けても発見には至らず、1月2日で捜索は打ち切られた。西大顛から西吾妻山あたりにかけての現場周辺は、新たな積雪によって一面真っ白な状態で、手掛かりとなるようなものはなにも見つけられなかったとのことである。
元日の谷川連峰・平標山では、40代の男性2人が山頂付近から滑走開始直後、数十メートル滑ったところでひとりのスノーボードがなにかにぶつかって折れてしまい、身動きがとれなくなるという事故が起きた。2人は110番通報して救助を求め、県警ヘリによって救助された。
また、北海道の富良野スキー場では12月29日、スキー場外でバックカントリー・スノーボードをしていたニュージーランド籍の49歳男性と45歳日本人女性が、急斜面で身動きが取れなくなり、午後4時過ぎに知人を介して警察に救助を求めた。2人は約5時間後に警察の山岳救助隊によって救助された。
同じ12月29日の夕方には、兵庫県の奥神鍋スキー場で40代と50代の男性2人がコース外の急斜面に落ち込んで動けなくなり、翌朝救助されるという事案もあった。
このケースでは、所持していたiPhoneの緊急通報サービス機能(携帯電話通信やWi-Fiの圏外でも人工衛星を経由して警察や消防、海上保安庁などに緊急電話をかけることができる機能)を使って消防に救助を要請し、消防は2人に「雪に穴を掘って寒さをしのいで」などとアドバイスを送っていたという。
バックカントリーでの遭難事故というと、ルートミスや雪崩による事故が真っ先に思い浮かぶが、この年末年始は深い雪への埋没や、滑走用具の紛失・破損による事故が報告された。バックカントリーには多様なリスクがあることを、再認識させられた。
爺ヶ岳と富士山での特徴的な遭難事故
バックカントリー以外では、12月31日に北アルプス・爺ヶ岳の標高約2500メートルの東尾根付近で、大学生の3人パーティ(23歳男性、21歳男性、20歳女性)が身動きできなくなり、救助を要請するという事故が起きた。3人は26日から入山していたが、同日午後、悪天候下でテントを張ってビバークしようとしたところ、強風でテントがはためいて破けてしまったという(テントが風で飛ばされたという報道もあったが、紛失はしていない)。警察は雪洞を掘ってビバークするよう指示を出し、翌1月1日の午前、県警ヘリで3人を順次救助した。3人は充分な大きさの雪洞が掘れず、浅い穴の中に入って破けたテントとツエルトで覆い、一夜を過ごした。女子大生は低体温症を発症しており、男子大学生にも凍傷のような症状がみられたが、命に別状はなかった。
冬山で寝泊まりするためのテントが破れてしまったのは致命的なアクシデントだったが、大事に至らず全員が救助されたのは幸いだった。冬山では自然環境が厳しいだけに、用具の破損が生死に関わる状況を招くこともある。また、休憩時などに脱いだ手袋や帽子が強風に飛ばされたり、雪の上に置いたザックが滑り落ちてしまったりするミスも散見されるので、何気ない所作にも充分な注意が必要だ。
年が明けた富士山の須走ルート九合目付近では1月2日、外国籍の登山者が、ケガをして行動不能となっている39歳男性単独行者を発見し、110番通報した。これを受けて静岡県警ヘリが出動したが、強風のため救助できず、山岳救助隊員らが地上から現場に向かった。そして遭難者を担架で吉田ルート五合目へと搬送し、通報からおよそ12時間後に救急隊員に引き継いだ。男性は全身を強く打っていて凍傷などの症状が見られたという。
報道によると、男性が富士山に登るのは、季節に関係なくこれが初めてで、その動機について「急に登りたくなったから」と警察に説明したという。行動不能に陥ったのは山頂近くから滑落したのが原因で、アイゼンやピッケルは携行していなかった。
ほとんど冬山経験のない人が、必携装備も持たずに冬の富士山に登ろうとして遭難するという事故は、数年に一度ぐらいの割合で起きている。積もった雪が強風で磨かれてカチンコチンに氷化した冬の富士山が、どれほど危険なのか。それを想像できないことが、ほんとうに不思議でならない。この事故について、登山家の野口健はSNSで「むしろ厳冬期の富士山にアイゼン・ピッケルなしで山頂まで登れたのがビックリ!!!」「しかし、ちょっと考えれば分かるだろうに。何のために脳みそがついているのだか…」とコメントしていたが、まったくそのとおりだと思う。
そのほか、南アルプス・北岳では12月31日、単独の50歳男性が池山吊尾根を下山中に、池山付近で滑落して右足首を骨折するという事故が、1月2日には同じ南アルプスの北沢峠八丁坂付近で、61歳男性単独行者が下山中に転倒して左足首を骨折する事故が起きている。また、長野県南牧村の飯盛山では1月2日に50歳女性が下山中に転倒して左足首を、1月3日には大月市の権現山で、50歳男性単独行者が下り坂で足を踏み外して左足首を骨折するという事故もあった。
いずれの遭難者も救助隊員やヘリコプターによって救助されたが、転倒や滑落などによって足を骨折する事故が目についた。しかも、登りではなく下るときに起きているのも特徴的だ。もともと下りでの転滑落や転倒による事故は多発傾向にあるが、冬は登山道が積雪などで滑りやすくなっているのも一因だろう。
なお、福島県猪苗代町の磐梯山では1月3日、登山者から「登山道の近くに人のようなものが倒れている」と警察に通報があり、防災ヘリが出動してピックアップしたが、その後、死亡が確認された。身元不明遺体は40〜50代とみられる男性で、登山をする服装だったという。警察は身元や死因などを調査中とのことだが、今のところ続報はないようだ。
以上、年末年始のいくつかの遭難事故について簡単に振り返ってみたが、その後もバックカントリーでの遭難事故はあとを絶たず、冬山登山中の事故も各地で起きている。本稿が公開されるころは厳冬期の真っ只中であり、冬山シーズンはまだまだ続く。山域によっては積雪が春まで残ることもあり、雪や寒さに対する警戒を怠ると痛い目に遭うことになる。油断せず、気を引き締めて、引き続き冬山を楽しんでいただきたい。

より困難を伴う雪山での遭難救助(写真はイメージです。写真提供:長野県警山岳遭難救助隊)
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』(山と渓谷社)がある。