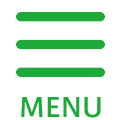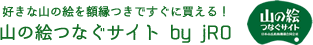オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|遭難の背景には”焦り”が。今、”予備日”を見直そう

事故後しばらくして蘇った記憶
私ごとで恐縮だが、先月、山と溪谷社より『ドキュメント生還2 長期遭難からの脱出』という本を刊行した。本書では、山で遭難し、救助されるまでに長い時間を要した4つの事故事例を取材・検証している。
その当事者のひとりから、刊行後間もなくしてメールをいただいた。彼のケースは、北アルプス後立山連峰の不帰ノ嶮でルートミスにより遭難し、8日後に救助されたというもの。本書を一読した彼は、ほかの事例で「早く帰るために焦って遭難してしまった人がいたことが印象に残った」といい、彼自身も遭難した当日は「そういった焦る気持ちが心の隅にあったことを思い出した」そうである。メールには、続けてこう綴られたいた。
〈天狗山荘から八方尾根のリフト乗り場まではコースタイムが約8時間の長丁場であり、リフトの最終に間に合うよう16時には到着しないといけない、のんびりはできない、という思いがありました。
その焦りがこまめに地図を確認しない行動となり、結果道迷いにつながったと思いました〉
彼とは対面で一度お会いして話をうかがい、原稿を書き上げたのちはメールで幾度となくやりとりし、修正を重ねたものを本に掲載した。その作業に少なからぬ時間をかけたので、この事例については詳細に検証できたと思っていた。だが、彼の記憶には、焦りが道迷いの一因になっていたことがすっぽり抜け落ちていた。
この例に限らず、遭難者が遭難中に体験したこと、考えたことなどをすっかり忘れていて、ある程度時間が経ったときにはっと思い出すという経験は、そう珍しいことではないようだ。予期せずに直面した遭難という極限の状況下で、さまざまな出来事や思いが交錯するうちに、あるものは意識の最下層に沈んでいってしまうのかもしれない。その奥底に仕舞い込まれていた記憶が、なにかがきっかけとなって頭をもたげてくるのだろう。
今回のように、検証記事を掲載した雑誌や本が刊行されたのち、しばらく経って当事者の方が、「そういえばあのとき、実は……」と新たに思い出した事実を知らせてくることは、たまにあったりする。
焦りが遭難事故を誘発させる
それはさておくとして、彼からのメールを読んで考えさせられたのが、〝焦りが遭難につながった〟という点だ。
振り返ってみれば、日常生活においても焦ってことを成すと、まずろくなことはない。約束の時間に遅れそうだと慌てて家を飛び出したときに、しばらくしてたいていなにか忘れ物をしてことに気づくというのは、よくある話である。締め切りの期日が間近に迫っていて、大急ぎで原稿を書き上げたはいいが、掲載された文章を読んで「あちゃ〜、ここはもうちょっと書きようがあったのではないか」とヘコんだりするのは、私だけだろうか。
その程度ですんでいるうちはまだいいが(よくないか)、登山中に焦りが生じると、冷静な判断・対処ができなくなって、危険な状況に追い込まれてしまうことが往々にして起こる。
2009年7月に起きた大雪山系・トムラウシ山での遭難事故では、ツアー登山の一行18人中8人が死亡するという大惨事になってしまったが、事故の直接的な要因となったのは、悪天候下で登山の強行を決めた判断だった。そう判断を下さざるをえなかった背景には、悪天候下でも当初の計画どおり行程を進めなければという〝焦り〟があったことは、想像に難くない。
登山を主催したツアー会社や、パーティを率いていた山岳ガイドらにしてみれば、計画の変更によって生じる諸々の煩雑な業務(下山後の宿泊施設や帰りの飛行機のキャンセル・取り直しなど)は、できれば避けたかったはずだ。計画の変更により、追加料金が発生する可能性ももちろん考慮しただろう。また、参加者の側にも「日程をオーバーせずに、予定どおりの期日に帰りたい」という思いがあったと聞く。
ところが、台風並みの暴風雨のなか、徐々にパーティの足並みは乱れはじめ、ガイドらは「日没までに参加者全員を安全に下山させられるのか」と焦りを募らせていく。その間にもいくつかの判断ミスが積み重なり、とうとう行動不能となる参加者が出るに至ってしまった。ここでガイドらの焦りはマックスまでに高まり、状況に対応しきれなくなってパーティは散り散りばらばらになってしまったのが、この事故だった。
こうして改めて事故の経緯を見てみると、ツアー自体が、出発前からガイドらに〝焦り〟を背負わせている、無理のある計画だったとしか思えない。
トムラウシ山のケースは、焦りが最悪の結果を招いてしまった最たるものだと思うが、毎年のように起きている沢の増水による事故も、焦りが大きな要因になっていると推測される。この類の事故は、登山道が沢を横切っている場所で、増水した沢を無理やり渡ろうとして流されてしまうというのが典型的なパターンである。とくに下山時は、「帰りの交通機関の時刻に間に合わせたい」「どうにしても今日中に下山しなければ」という思いが強い。その焦りから、冷静に判断すれば危なくて渡れそうもない流れなのに、「なんとかなるだろう」と思ってしまうようだ。しかし、水流の力というのは見た目以上に強大で、膝下ほどの水深でもあっという間に足がすくわれてしまうこともある。かくして命を落としてしまう登山者が、残念ながらあとをたたない。
生死に関わらないまでも、同様のことは日帰りのハイキングでも起こりうる。休憩中についのんびりし過ぎて、気がついたら帰りの最終バスの時刻が迫っていた、あるいは日没間近になってしまっていた、といった経験がある人は案外多いのではないかと思う。そこで焦って先を急ごうとすると、道に迷ったり、つまずいて転倒したりと、さらなる悪いことが起きてしまう。
「予備日」を設定することの大切さ
日常であれ山であれ、とにかく〝焦り〟は不吉の前兆だと思ったほうがいい。そもそも焦ってしまうのは、たいていの場合は時間に余裕がないときだ。統計的な根拠があるわけではないが、今起きている遭難事故の多くも、時間的な余裕のなさが根本的な原因になっているのではないだろうか。逆にいえば、時間的に充分な余裕があれば防げる遭難事故も多いということになる。
遭難事故防止を説く際の決まり文句のひとつ、「余裕を持った計画を立てましょう」というのは、実はとても大切なことなのだと思う。
そこで思い起こされるのが、悪天候やアクシデントによる行動の遅れに備えるための「予備日」である。かつては、登山計画を立てるときに予備日を設けるのは当然だった。厳冬期の北アルプスなど困難な登山の場合は、ふつうに1週間以上の予備日をとっていたものだった。
しかし今、計画段階で予備日をとっている登山者はどれぐらいの割合でいるのだろうか。
なにしろ日本人は勤勉だし現代人は忙しい。忙しい仕事の合間を縫って登山の予定を組んでいるような状況では、予備日をとるだけの余裕はないかもしれない。
だが、たとえば無雪期の2、3日の山行であっても、1日は予備日を設けたほうがいい。予備日をとることで時間に余裕ができれば、気持ちにもゆとりが生まれ、焦りがもたらすアクシデントを回避することにも繋がる。
遭難しないために、予備日を設定することの意味を、今一度考えてみてはいかがだろうか。
なお、もし予備日をとらずに山に来て、下山予定日に下りられなくなってしまっても、焦る必要はない。「下りられない」と判断した時点で、「よし、明日は予備日だ」と、自分で決めて気持ちを切り替えればいいのだから。
これまで取材してきた遭難者のなかには、無理して予定どおり行動しようとして遭難してしまい、生死の境を彷徨ってようやく助けられた人が何人かいた。彼らは異口同音にこう言っていた。
「なぜ無理してまで下りようとしたのか。焦って無理したせいで、何日間も山のなかで命の危険にさらされることになってしまった。無理しなければ、下山が一日遅れただけで済んだのに」
下山が遅れたことで騒ぎになったとしても、大事な仕事に穴を開けたとしても、焦って下りようとして遭難してしまうよりは、よっぽどマシだと思うのだが。

羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』(山と渓谷社)がある。