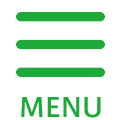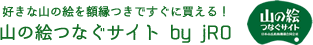オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|セルフレスキューのノウハウは登山者の必須装備

ファーストエイドキット、携行していますか?
セルフレスキューの重要性
山で遭難した際の救助活動には、「セルフレスキュー」と「チームレスキュー」の2つがあることをご存知だろうか。
セルフレスキューはその名のとおり「自力救助」のことで、事故当事者やパーティの仲間、周囲に居合わせたほかの登山者などが行なう初動救助を意味する。これに対し、警察や消防、民間などのプロフェッショナルな救助隊によって行なわれる組織的な救助活動がチームレスキューだ。
登山は原則的に〝自己責任〟で行なうものだから、登山中に発生するアクシデントやトラブルは自分たちで対処・解決し、最終的に自力で下山してくるのが本道である。社会人山岳会や大学山岳部が活発に活動していたころは、遭難事故が起きると会や部の仲間が現場に駆け付けて自力で救助するのが当たり前だった。つまり遭難救助活動はセルフレスキューのみで完結していたわけである。
しかし、時代が変わって山岳会などに所属しない未組織登山者が登山人口の大半を占める今、「登山は自己責任なんだから、自分たちでどうにかしろ」lというのは無理があるし現実的ではない。そもそもチームレスキューには、ヘリコプターなどの機動力と最新のレスキューノウハウが備わっているのだから、万一のときにこれを頼らない手はない。
救助をセルフレスキューに頼っていた時代は、人力で遭難者を担ぎ下ろしてくるのに長い時間がかかり、搬送途中で息を引き取ってしまうことも少なくなかったと聞く。それが今では、チームレスキューのおかげで迅速に医療機関に搬送することができ、適切な処置を受けられるようになった。このため救命率は格段に上がり、早期の回復や社会復帰が見込めるようになっている。
ただ、事故が起きたらすべてをチームレスキューに委ねればいいのかというと、そうではない。現場から携帯電話で救助要請ができたとしても、街中のように10分前後で救急車が駆け付けてきてくれるわけではない。ヘリコプターが救助隊員が現場に到着するまでには、やはりある程度の時間がかかってしまう。
その数時間の間に行なわなければならないのがセルフレスキューだ。
セルフレスキューの内容には、遭難者の状態確認、安全な場所への退避、傷病に対する応急手当、遭難者の保温などが含まれる。現場にいる者にこれらのノウハウがなく、なにもできないまま救助隊の到着をただ待つだけでは、遭難者をいっそう危険な状況に追い込んで、場合によっては助かるものに助からなくなってしまう。
逆にセルフレスキューが適切に行なわれ、チームレスキューへのスムーズな引き継ぎができれば、救助を待つ間の遭難者の苦痛を軽減でき、助かる確率も高くなる。
その救助要請の判断は適切だったか
ところが、遭難事故を報じる最近のニュースを見ていると、「チームレスキューを呼ぶ必要があったのか」「セルフレスキューだけで対処できたのでは」と首を傾げてしまうケースが少なくない。たとえば次に挙げるような事例だ。
- 北アルプス・涸沢/2023年9月18日、奥穂高岳を目指して上高地から入山した70歳の男性単独行者が、本谷橋付近でバランスを崩して約2m滑落、左肘を擦りむくなどの軽傷を負った。男性は救助を要請したが、自力で歩行できたため、合流した救助隊員に付き添われながら下山した。
- 北アルプス・燕岳/2024年5月19日の夕方、燕岳を登山していた46歳男性と44歳女性の2人パーティが、北燕岳の山頂付近で転倒して足を負傷し、警察に通報した。このときは「自力で下山できそうだ」という話になり、2人は下山を続けたが、翌日の午前4時半ごろ、再度警察に連絡を入れ、「自力で動けない」と救助を要請した。2人は現場に駆けつけた救助隊員に伴われて下山した。男性は疲労しているもののケガはなく、女性は左膝打撲の軽傷だった。
- 北アルプス・唐松岳/2024年7月7日、唐松岳から八方尾根を下山していた7人パーティのうち、68歳の男性が転倒してケガをし、同行者が警察に救助を要請した。県警ヘリコプターで松本市内の病院に搬送された男性は、額を負傷する軽傷だった。
- 妙高山/2024年7月13日、夫といっしょに燕温泉登山口から妙高山に入山した60代の女性が、9合目付近の鎖場を上り切ったところで両足が攣って行動不能に陥った。夫からの110番通報を受けて警察と消防の救助隊員が出動したが、その後、女性は自力で歩行できるまで回復し、隊員に付き添われて下山した。
- 八ケ岳・天狗岳/2023年7月22日、単独で天狗岳に登っていた56歳の女性が、山頂から唐沢鉱泉へ向けて下山中に、足を滑らせて転倒した。本人からの救助要請により警察と消防の救助隊員が出動し、唐沢鉱泉まで付き添って下山した。女性は軽傷のもよう。
事故発生時にはまずセルフレスキューで対応を
これらは新聞やテレビなどで報じられた概要的なニュースなので、詳細な経緯についてはわからない。いずれの遭難者も軽傷(症)だったようだが、もしかしたらあとになって重傷(症)だったことが判明していたかもしれない。なにより当事者が「もう自力では行動できない」と判断した以上、「いやいや、まだがんばれるでしょう」とはいえないし、助けを求めている人がいれば助けるのが救助隊の任務である。
しかし、それは理解しているつもりだけど、どうしてもモヤモヤ感が残ってしまう。というのも、「救助を要請するのが早過ぎたのでは」という印象は否めず、つい「セルフレスキューで対処できたのではないか」と勘繰りたくなってしまうからだ。
なんらかのアクシデントによって登山中に傷病を負ったとき、まず行なうのは傷病の程度の確認である。それが明らかに重傷(症)で一刻を争う場合は、速やかに救助を要請しなければならない。だが、危急性が認められなければ、応急手当を施したうえで、傷病者の状態や今後の行程などを考慮し、救助を要請するのか自力で行動を続けるのか判断すべきだろう。
上記の事例に関していえば、不測の事態で気が動転してしまったのか、当事者は慌てて救助を要請してしまった感がある。彼らにセルフレスキューのノウハウがあったかどうかはわからないが、冷静に対処してセルフレスキューができていれば、自力で下山できたのでは、と思えてならない。
昨年のこのコラムでも触れたが、「疲れたから」「足が攣ったから」「転んで足を擦りむいたから」といったような理由で救助を要請するケースが、昨今はあとを絶たない。それは今年の夏山シーズンも然りで、救助隊員の主要任務は〝遭難救助〟ではなく、ますます〝下山介助化しつつある。
もちろん、重傷(症)を負っているのに、無理してまで自力下山にこだわるのは賢明ではない。素直にチームレスキューの力を借りるのが、最良の判断というものである。
だが、セルフレスキューによって対処できるのであれば、まずはそれを試みるべだろう。そのうえで自分たちの手に負えそうになければ、救助を要請すればいい。
登山を長く楽しんでいくには、さまざまな知識や技術の習得が必要になってくるが、セルフレスキューのノウハウもそのなかに含まれる。少なくともファーストエイドキットは必携装備とし、応急手当の方法(心肺蘇生法や止血法、捻挫・骨折・熱中症・低体温症などの対処法)についてもしっかり学んでいただきたいと思う。

セルフレスキューや救急法の講習会に参加してノウハウを学んでおこう
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』(山と渓谷社)がある。