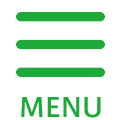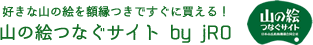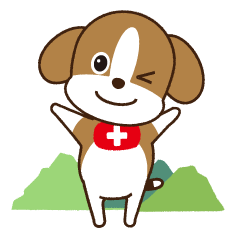オサムの“遭難に遭う前に、そして遭ったら”|春到来でも油断は禁物。4、5月にも雪崩事故は起きる

春の雪山にはまだまだ雪崩のリスクが存在する
寒さが厳しく大雪に見舞われた今年の冬
顕著な暖冬だった2023〜24年の冬とは打って変わり、今シーズンは全国的に厳しい寒さとなった。昨年12月から今年の2月にかけて、冬型の気圧配置が続いた影響で持続的な低温傾向となり、とくに2月には強い寒波が相次いで襲来して、日本海側を中心に記録的な大雪となった。帯広市では2月4日、12時間降雪量が120センチに達し、国内観測史上最多を記録して話題となった。2月20日の午後1時には、豪雪地帯として知られる八甲田山麓の酸ヶ湯で積雪が5メートルに達したが、5メートルを超えたのは2013年以来12年ぶりで、1979年の観測開始以来3度目だという。
こうした要因について、気象庁は去る3月18日に「異常気象分析検討会」を開き、「高緯度帯と中緯度帯を流れる2つの偏西風が、日本付近で南に蛇行したことにより、強い寒気が流れ込みやすくなった」とする見解をまとめた。大雪については地球温暖化の影響を指摘、気温や海面水温の上昇に伴って大気中の水蒸気量が増加し、気温が低い地域に強い換気が流れ込んだことで降雪量が増えたと説明した。
3月に入ってからは寒暖の差が激しく、寒気の流入により都心で雪が降った日もあれば、一転して汗ばむような初夏の陽気になった日もあった。気象庁が3月25日に発表した3ヶ月予報によると、4、5月は全国的に数日周期で天気が変わり、平年同様に晴れの日が多く、気温は平年並みか高めとのことである。
さて、そこでちょっと気になるのが春の雪崩である。本稿を執筆している3月下旬現在、ほぼ毎日のように北海道や東北、甲信越、北陸、中国地方などに「なだれ注意報」が出されている。この冬の大雪により山岳地でも例年より積雪が多いという話を聞くと、単純に雪崩のリスクが高くなっているのではないかと思ってしまう。
これまでに起きた春の雪崩遭難事故
実際、雪崩による遭難事故は4月以降にも少なからず起きている。たとえば2013年のゴールデンウィークの事故。このとき北アルプスでは、連休前から真冬並みの天気となって雪が降り続き、白馬大雪渓では4月27日早朝から入山自粛要請が出されていた。しかし、「天候回復が望める」と判断して入山した50代の男女6人パーティのうち4人が、午前10時35分ごろ大雪渓で発生した雪崩に巻き込まれてしまった。4人のうち3人は仲間に救出されたが、56歳の女性が行方不明となり、翌日、遺体で発見された。死因は窒息死だった。
この雪崩には、自粛要請が出される前日に入山していた2人パーティ(32歳と50歳の男性)も巻き込まれていたことが判明し、後日、それぞれ遺体となって発見された。やはり死因は窒息死だった。
同じゴールデンウィークの白馬大雪渓では、2011年と2017年にも雪崩による死亡事故が起きた。 2011年の事故は4月29日の午後4時ごろ、下山中だった9人パーティのほか複数の登山者が、幅約100メートル、長さ約1キロの雪崩に巻き込まれ、3人が死亡、2人が重軽傷を負った。2017年の事故の発生は4月28日の午後0時半過ぎ。大雪渓上部で長さ約300〜400メートル、幅60〜70メートルの雪崩が起き、下山中の男性2人パーティが巻き込まれた。ひとりは自力で脱出したが、37歳の男性が行方不明となり、翌月20日、捜索していた山仲間らが遺体を発見した。
この事故の2日後の4月30日午後2時過ぎには、剱岳の源次郎尾根でも雪崩が発生し、男性登山者2人が巻き込まれた。それを近くにいた富山県警山岳警備隊員が目撃していたため、ただちに隊員とヘリコプターによる捜索が行なわれ、63歳の男性を救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は窒息死。もうひとりは自力で脱出して無事だった。
2010年5月1日には、立山連峰の御山谷の出合付近に巨大な雪の塊が落下する事故も報告された。時刻は午前11時50分ごろ、下山中だった10人パーティのうち2人がこれに巻き込まれ、60歳男性が死亡、もうひとりも大ケガを負った。起きたのは雪の塊が崩れ落ちる「ブロック雪崩」だったとみられ、亡くなった男性の死因は外傷性窒息だった。この日は剱岳の早月尾根上部でも雪崩が発生し、48歳男性が巻き込まれて滑落、命を落としている。
これらのほかにも、私の知るかぎり次のような雪崩事故が春に起きている。
●2011年4月17日/午前9時50分ごろ、谷川連峰のコマノカミノ頭の山頂付近で、幅4メートルほどの雪崩が発生し、登山中だった38〜64歳の男女7人パーティのうち4人が巻き込まれた。ひとりは軽傷、3人は肩や足などを骨折する重傷を負ったが、命に別状はなく、県警ヘリコプターによって救助された。
●2013年4月23日/バックカントリー・スノーボードをするために単独で北海道の富良野岳に入山した42歳男性が帰宅せず。道警や友人が捜索したところ、中腹の三峰山沢付近で深さ20センチほどの雪に全身が埋まっている男性を発見し、病院へ搬送後、死亡が確認された。近くには幅約50メートル、長さ約200メートルの雪崩の跡があったことから、スノーボード中に雪崩に巻き込まれたものと見られている。
●2018年5月26日/谷川岳に入山した男女5人パーティが、マチガ沢で雪上訓練を行なう準備をしていた午後1時ごろ、雪崩が発生して24〜56歳の3人が巻き込まれた。3人は数メートル流され、それぞれ肋骨骨折や顔面挫傷などの重傷を負い、県警ヘリで救助された。
●2022年4月1日/午前10時ごろ、八ヶ岳の赤岳山頂付近で長さ200メートル、幅10〜15メートルの規模の雪崩が発生し、登山中だった3人パーティのうち2人が巻き込まれた。ひとりは自力で脱出して無事だったものの、翌日発見された65歳の男性は死亡が確認された。死因は頸椎損傷だった。
●2022年5月29日/訓練のため飯豊連峰の北股岳へ向かって石転び沢を登っていた陸上自衛官7人の一隊に、午後0時15分ごろ、上部の雪渓から雪の塊が落ちてきて、35歳と46歳の自衛官2人が負傷した。2人は足や腰に打撲を負って自力下山できなくなり、自衛隊のヘリで救助された。
今しばらくは雪崩への警戒を
今春の天気ついて、「数日周期で天気が変わる」という気象庁の予報を先に紹介したが、春は高気圧と低気圧が交互にやってきて気圧配置が目まぐるしく変わるので、もともと天気が変わりやすい季節である。
とくに低気圧や前線の通過後に寒気が流れ込んだり、冬型の気圧配置になったり、メイストームのように低気圧が急速に発達したりすると、大荒れの天気となることも珍しくない。山岳地は真冬に逆戻りし、一定の降雪があれば、当然、雪崩のリスクも高まる。
また、暖かい空気が流れ込んでくる気圧配置になって気温が上昇すれば、全層雪崩やブロック雪崩への警戒も必要となる。
里や街はうららかな春の陽気であっても、高い山ではまだまだ雪崩は起こりうる。この春に雪山登山やバックカントリーを計画している人は、充分注意していただきたい。

雪崩のリスクに備えた計画や装備を
羽根田 治(はねだ おさむ)
1961年埼玉県生まれ。那須塩原市在住。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員。山岳遭難や登山技術の記事を山岳雑誌などで発表する一方、自然、沖縄、人物などをテーマに執筆活動を続ける。『ドキュメント 生還』『人を襲うクマ』『山岳遭難の傷痕』(以上、山と渓谷社)など著書多数。近著に『山はおそろしい 』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか』(平凡社新書)、『これで死ぬ 』『ドキュメント 生還2 』(山と渓谷社)がある。