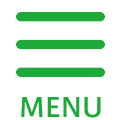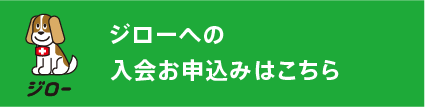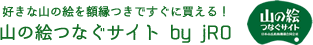羽根田治の安全登山通信|2012年ゴールデンウィークの遭難事故を検証する
- ホーム
- > 自救力
- > 羽根田治の安全登山通信
*2012年のゴールデンウィークに起きた事故について、『山と溪谷』7月号に4ページの記事を寄稿しました。執筆した原稿は、記事の倍ぐらいの文字数になってしまったため、泣く泣く削ってなんとか4ページに収めたのですが、せっかくあちこち取材して書いた文章なので、この場を借りてオリジナルに近い原稿を公開することにしました。ヤマケイと読み比べていただければ幸いです。
北アルプス・白馬岳を登山中の6人パーティと連絡がとれない、という家族からの届け出が大町警察署にあったのは、5月4日の午後5時40分ごろのことである。6人は北九州市の医師ら63〜78歳の男性で、前日3日に栂池高原スキー場からゴンドラリフトを利用して入山。栂池ヒュッテに1泊し、この日は白馬乗鞍岳、小蓮華山、白馬岳を経て白馬山荘に宿泊する予定だった。ところが夕方になっても到着しないことから、山荘のスタッフが家族に連絡し、家族が大町署に届け出たのだった。
6人が栂池ヒュッテを出発したのは朝5時ごろ。このときの天候は無風で青空ものぞいていたという。ところが、午後になって天候が急変した。この日、6人とほぼ同じコースをたどった単独行の登山者は、白馬山荘のスタッフに「船越ノ頭で稜線に出たとたん、みぞれ混じりの強烈な向かい風に見舞われた」と言っていたそうだ。彼が小蓮花山に着いたのは午後1時ごろで、振り返ってみると下のほうに6人パーティが見えたという。
また、新聞報道によると、午後1時半ごろ、小蓮華山から白馬大池方面に10分ほど下った地点で6人とすれ違った10人パーティがおり、そのなかのひとりがすれ違う際に「先生、どうしましょうか」という話し声を聞いている。状況から推測するに、6人はこのまま前進するか引き返すかの相談をしていたものと思われる。
届出を受けた大町署の署員は、6人全員が所持していた携帯電話に次々電話をかけてみたが、5人はつながらず、もうひとりは呼び出し音はするものの応答がなかったという。
翌5日の朝5時40分、長野県警ヘリが松本空港を飛び立って6人の捜索に向かったが、場付近の稜線には雲がかかっており風もそうとう強かったため、接近できないままいったん帰投した。その後、午前8時ごろになって、白馬岳北方の三国境付近を通りかかった登山者が稜線で倒れている6人の登山者を発見、白馬山荘を通じて警察に通報した。
天候が若干回復した8時20分、県警ヘリが再度、現場へ向かったところ、小蓮華山で滑落した別の登山者を発見。まずこの遭難者を救助したのち、再び現場へ引き返していき、9時41分、通報どおりの場所で6人が倒れているのを発見した。
6人のうち5人はひとかたまりになっていて、2人は手袋をしていなかった。素手でなにか作業をしようとしたのだろうか、そばには脱いだ手袋が落ちていた。もうひとりはその場から滑落したもようで、100mほど下のところに倒れていた。
「何人かは生存しているものと思って早朝から無理して飛んだんですが……。まさか6人全員亡くなっているとは思っておらず、ショックでした」(長野県警航空隊・櫛引知弘隊員)
遭難者の体の一部(風上側)は厚さ10cmほどの氷漬けとなっていて、地面に張り付いていた。このため、救助隊員は体を傷つけないようにピッケルで氷を割り、動かせるようにしてからヘリコプターに収容した。
「通常、吹雪だったら雪がエビのしっぽ状に着くはずなのに、つららが成長していくような感じで氷が付着していました。たぶんみぞれのような雪が猛烈な風によって氷化したのでしょう」(櫛引隊員)
遭難者は2人ずつ3回に分けて搬送されたが、最後はガスがかかってきてしまい、間一髪の収容となった。遭難者といっしょにザックも回収するつもりだったが、そばにあった2つのザックを回収するのがやっとだった(ほかの荷物は、後日、白馬村山岳遭難防止対策協会の隊員が回収した)。6人の死因は、いずれも低体温症であった。
白馬岳の6人の遭難が懸念されはじめていた4日の夕刻、 種池山荘のオーナー・柏原一正氏の大町市内の自宅に、女性登山者(大阪市・62歳)から一本の電話がかかってきた。開口一番、女性は「何度もかけて、やっとつながった」と言い、「吹雪でなにも見えない」と続けた。ところがそのあとすぐに電話は切れてしまい、以降、つながっては少し喋って切れるというやりとりを何度も繰り返すことになる。その切れ切れの会話で判明したのは、女性が朝7時に扇沢から爺ヶ岳を目指して登山を開始したということであった。
扇沢から爺ヶ岳へ登るには通常、柏原新道をたどっていくが、まだ雪のあるこの時期は上部が通行不能になっているため、下部でコースを外れて尾根伝いに登り、合流した南尾根を詰めて爺ヶ岳の南峰に直接出るルートをたどっていくことになる。当然、女性もこのコースをたどったものと思われたが、では今どこにいるのかがはっきりしなかった。柏原氏が「ジャンクションピーク(南尾根上の一ピーク)は過ぎたのか」「樹林帯は越えたか」「南峰には着いたのか」と尋ねても、曖昧な答えしか返ってこないのだ。「赤旗が立っている」というのが唯一の情報だったが、赤旗は南尾根の上部および爺ヶ岳南峰〜冷池山荘間に何本も立ててあるので、その情報だけでは位置を特定できない。
それにしても朝7時に扇沢から歩き出して、午後5時になってもまだ冷池小屋に到着していないのは、いくらんでもペースが遅すぎる。柏原氏が「ずいぶん時間がかかっているね」と言うと、女性は「休み休み来たものだから」と答えたという。
「とにかく現在地がまったくわかっていなかったし、南峰まで登ったのかどうかもはっきりしない。話の様子からして、コースを全然把握していないし、山にも慣れていない印象を受けました。もしかしたら、夏道と冬道が違っていることを知らなかったのかもしれません。南尾根をたどりながら、本人は柏原新道を歩いているつもりだったのでは」
腑に落ちないのは、女性がひとことも「助けてください」「救助を要請してください」といった類いの言葉を言わなかったことだ。「もう諦めてぼちぼち下りますわ」と伝えてきたので「大丈夫か」と尋ねると、女性は「はい、大丈夫です」と答えた。ヘッドランプも持っているという。
「非常に落ち着いていて、切迫感はまったくありませんでした。だからそれほどひどい状況だとは思わず、南尾根の標高2500mあたりまでは下ってきているのだろうと考えていたんですが……」
最後の電話が掛かってきたのは午後5時半ごろ。「もう電源がない」と言って切れ、以降、電話はつながらなくなった。いくら本人が「大丈夫だ」と言っていたとしても、この状況下ではさすがに心配になり、柏原氏は警察に一報を入れるとともに、警察の許可を経てひとりで現地へ捜索に向かった。
自宅を出て扇沢に着いたのが午後7時ごろ。7時10分から登りはじめ、支尾根が南尾根に合わさるジャンクションピークには9時半に到着した。ピークにはテントが4張あり、それぞれのパーティに「単独行の年配の女性登山者を見なかったか」と聞いてみたところ、2パーティが女性に行き合っていた。その2パーティはやはり扇沢から爺ヶ岳を目指していたが、悪天候のため途中で撤退を決め、南尾根を下山してくるときに登ってきた女性とすれ違ったという。
その情報を得た柏原氏は、ジャンクションピークの上あたりまで女性が下ってきているかもしれないと思い、10時すぎまであたりを捜して歩いたが、目も開けていられないほどの猛吹雪のため捜索を断念し、諦めて11時過ぎに下山した。
翌5日、爺ヶ岳に登った登山者が、中央峰と北峰の鞍部付近に倒れている女性登山者を発見したのは午前7時ごろのことである。午前11時40分、女性は長野県の消防防災ヘリによって収容され、前日から行方不明になっている単独行者であることが判明したが、すでに息を引き取っていた。死因は低体温症と見られている。
4日午後になって猛吹雪が荒れ狂ったのは、後立山連峰だけではない。前日に上高地から入山した福岡県の56〜71歳の男女6人パーティは、4日朝、宿泊していた涸沢小屋を出発し、北穂高岳を経て穂高岳山荘を目指していた(6人が北穂高小屋に立ち寄ったかどうかは不明だが、立ち寄ったのを記憶している小屋のスタッフはいないという)。ところが、オダマキのコルまで来たところで、61歳の女性メンバーが悪天候による低体温症で行動不能者に陥ってしまった。時刻は午後3時〜4時の間だったそうだ。
このため、リーダーともうひとりのメンバーが女性に付き添ってその場に留まり、ほかの3人が穂高岳山荘に救助を求めに向かったのだが、その3人も涸沢岳に登り着いたと同時に猛烈な風雪に見舞われ、身動きできなくなってしまう。3人はなんとか山荘へのルートを探そうとしたものの、猛吹雪のなかでは方向が定められず、午後5時ごろにはやむなくビバークの態勢に入ったという。
「涸沢岳の山頂から山荘まで、ふだんだったら10分かからないんですが、あのコンディションでは、どっちに行けばいいのか、方向がわからなかったと思います。たとえコンパスがあったとしても、風速20mもの猛吹雪のなか、風を避ける場所もないところなので、果たして動けたかどうか……」(穂高岳山荘スタッフ)
穂高岳山荘に常駐していた岐阜県警山岳警備隊に救助要請の電話が入ってきたときは、すでに午後7時を回っていた。電話はオダマキのコルで女性に付き添っていたリーダーからのもので、「ああ、やっと通じた」という第一声から、それまで何度も連絡をとろうとしていたことがうかがえた。また、この通報により、先発隊の3人がまだ小屋に着いていないことも判明した。
要請を受け、3人の警備隊員がただちに現場へと出動し、遅れて穂高岳山荘のスタッフ4人がそのあとを追った。吹雪は依然おさまっておらず、風速は15〜20m、視界は20〜30mほど。自分の庭のように周辺の地形を熟知しているはずの山荘スタッフが束の間、方向がわからなくなるほどの激しい風雪のなかでの出動であった。
警備隊員が涸沢岳の山頂に上がってみると、そこにビバークしている3人の遭難者がいた。
「3人はひとかたまりになってツエルトを被っていました。この時点では3人ともわれわれの問いかけに応じられるくらい意識ははっきりしていて、なんとか自力で行動できそうに見えました」(岐阜県警山岳警備隊・佐々木拓磨隊員)
この3人を救出すべく下降点の設置作業を行なっているところへ、後発の山荘スタッフ4人が合流した。そこで救助隊は二手に分かれ、3人が涸沢岳で救助作業を引き継ぎ、ほかの4人はその先のオダマキのコルへと向かった。
ところが、下降点の設置を終え、3人を山荘に連れ帰ろうとしたときに、アクシデントが発生する。パーティのなかでいちばん高齢だった71歳の男性が、低体温症の進行によって意識朦朧となり、自力で行動できなくなってしまったのだ。悪天候・夜間・急峻な岩場という悪条件のもと、3人の遭難者を3人だけで救助するのは無理がある。やむなく山荘に応援を求め、新たに数人のスタッフらが駆けつけてきて救助活動に加わった。
行動不能となった男性を背負ってどうにか山荘まで運び込んだのが午後9時過ぎ。男性はこの時点ですでに心肺停止状態に陥っており、警備隊員がただちに心肺蘇生を開始した。ほかの2人の遭難者は、スタッフらのサポートを受けながら自力で山荘にたどり着いた。
一方、オダマキのコルに向かった4人が現場に到着してみると、最初に低体温症になった女性が意識朦朧とした状態でおり、そばに男性2人が成す術もない様子で付き添っていた。3人はいちおうツエルトを被っていたが、女性の半身は外に出ていて、あまり用を成していなかった。この行動不能の女性を警備隊員と山荘スタッフが交代で背負い、ほかの2人は自力で歩けるリーダーともうひとりのメンバーをフォローしながらあとに続いた。
だが、涸沢岳まで来たところで、とうとうリーダーが力尽きて倒れてしまう。このリーダーを搬送するために、再び山荘から応援部隊が投入された。先行していた女性は10時前に山荘に運び込まれ、もうひとりの遭難者はなんとか自力でたどり着き、最後にリーダーが11時前後に収容された。
現場で指揮に当たった岐阜県警山岳警備隊の川地昌秀隊員は、次々に遭難者が運び込まれてくる模様を、「まるで野戦病院のような状況だった」と形容した。6人の遭難者は全員が大なり小なり低体温症に陥っており、山荘のスタッフが総出で応急処置に当たった。この日、山荘の主泊客のなかに医師と看護師がおり、騒ぎを聞きつけて「なにかできることがあれば」と協力を申し出、夜を徹して治療に当たってくれた。
いちばん最初に収容された男性は30分以上に渡って心肺蘇生を受けたが回復せず、医師によって死亡が確認された。意識朦朧としていた女性は加温措置によって持ち直し、約3時間後には正常な状態に回復しつつあった。その女性よりも重症だったリーダーは半ば錯乱状態に陥っていたが、医師やスタッフらの懸命な処置によって朝方には回復した。
山荘スタッフのひとりが、このときのことを振り返ってこう言う。
「現場がオダマキのコルだったから救助できましたが、それより遠かったら救助は翌日以降になっていたでしょう。また、たとえ小屋に遭難者を運び込んでも、低体温症に対する処置ができていなければ、間違いなくあと2人は亡くなっていたはずです。そういう意味で、できることぎりぎりの状況下での、総力戦の救助活動でした」
なお、この遭難事故の2日後の6日、新穂高から入山してジャンダルムの飛騨尾根を登攀した愛知の山岳会の男性3人パーティが、奥穂高岳から間違い尾根に入り込んで滑落するという事故が起きた。3人ののうちひとり(38歳)は自力で尾根に登り返して救助を要請したのだが(本人は長野側へ滑落したものと思い、110番通報してそう告げた。電話は岐阜県警から長野県警に転送され、最初は長野県警の救助隊が出動したのだが、のちに岐阜県側での案件であることが判明する。長野県警はそのまま救助を続行)。このとき現場に駆けつけていったのも穂高岳山荘のスタッフだった。
奥穂高岳の山頂付近で確保された男性は、軽度の低体温症にかかっていたが自力で歩行できたため、スタッフが付いて山荘まで下山した。
この救助活動中、吹雪のなかから男性登山者が突如「あの〜」と声をかけてきてスタッフを驚かせた。大阪市からやってきたその男性(55歳)は3日に単独で上高地より入山。北尾根から吊尾根経由で5日に奥穂高岳山頂に到達したが、悪天候のため下山できず、頂上付近に雪洞を掘ってビバークしていた。そこへたまたま穂高岳山荘のスタッフが現れたため、助けを求めたのであった。
最初のうちは元気そうに見えた男性は、スタッフといっしょに山荘へ向かう途中、みるみるうちに弱ってきて、とうとう自力で歩けなくなってしまった。幸い涸沢に常駐していた長野県の山岳救助隊員がサポートに駆けつけてきてくれたため、どうにか担いで下ろすことができたのだが、低体温症の進行により昏睡状態と錯乱状態を夜中まで繰り返した。その後は徐々に容態が落ち着いてきて、朝にはすっかり回復していたという。
間違い尾根から転落して行方不明になっていた愛知の男性2人(35歳と31歳)は、翌朝発見され、岐阜県警のヘリコプターで収容されたが、すでに亡くなっていた。死因はやはり低体温症であった。
北アルプスで3件の事故が起きた5月4日、現場周辺の複数の山小屋関係者は、「朝の天気はそれほど悪くなかった」と口を揃える。
〈(前日からの)雨は大降りにはならず今朝まで霧雨程度で推移してきました。9時頃からはその雨も止み、時たま薄日が差して外は明るくなるものの、キリの中から抜け出せません。早くすっきり晴れて欲しいですね。気温は11時現在+5℃、今日はあまり気温が上がらず肌寒い感じです〉
4日のブログにこう綴っているのは、白馬山荘スタッフだ。また、長野県警航空隊の櫛引隊員は、「ガスで稜線は見えず、風もそこそこ吹いていた」と言うが、朝方1時間ほど、槍・穂高連峰で行方不明になった単独行の登山者をヘリコプターで捜索している(後日、南岳の山頂付近で遺体が発見される。死因はやはり低体温症と見られている)。つまりヘリコプターを飛ばせないほどの悪天候ではなかったということだ。
ところが、昼前後から天候が急変した。
「昼前から天候が崩れ出し、ぐんぐん気温が下がってきました。最初はみぞれ混じりの雨だったのが、午後になって吹雪に変わりました。警備隊員になって10年以上経ちますが、これほどいっきに風が強く吹き出したのは経験したことがありません。自分としては急変したな、という認識でした」(岐阜県警・川地隊員)
「いったんやんだ雨がしばらくしてまた振り出し、それが雪に変わりました。午後になって風が出はじめたかなと思ったら、瞬く間にブリザードのような吹雪になってました」(白馬山荘スタッフ)
この日、小誌の前編集長も、猿倉から小日向のコルに向かう途中の午後3時ごろ、天候の「激変」に遭遇する。つい1時間前までは青空が見えて半袖で歩けるほどの暖かさだったのに、西からやってきた黒雲が天を覆ったのと同時に気温が一気に下がり、冷たい雨が落ち始めたのだ。それから10分もしないうちに雨は横殴りとなり、午後4時には完全な暴風雨に変わっていたという。標高2000mに満たない場所でこの状況だったのだから、3000mの稜線上は猛烈な吹雪になっていたことは想像に難くない。
「あの日の天候の変化はまさに突発的で、荒れ方も尋常ではありませんでした。たとえ装備が完全であったとしても、あの時間帯に吹きさらしの稜線にいたということだけで、生存の可能性は限りなくゼロに近かったと思います」
ただ、急変したことはさておき、この日の天気が芳しくないのは事前に予想されていたことだった。「3、4、5日は天気が悪くなるという予報だったので、『予報どおりだな』という印象でした」と言うのは北穂高小屋のスタッフである。長野県警・櫛引隊員も、「一般登山者がどれだけ認識していたかわかりませんが、上空に寒気が入ってきて山が荒れるのは事前にわかっていたことでした」と言っている。
また、気象予報士・猪熊隆之氏は、日本山岳会の春山天気予報配信にて、北アルプスにおける4日の荒天をぴたりと的中させている。
「4日の天候は冬山の気象の典型的な疑似好天パターンでああり、予想天気図をチェックしていれば天候の変化は予測できたはずです」(猪熊氏)
さて、悪天候が予想されるとき、あるいは悪天候に遭遇してしまったときにまず考えなければならないのは、どの時点でどういう判断(計画を決行するか撤退するか)を下すか、だ。それを誤ると、悪天候につかまって命を落としてしまうことになる。
白馬岳で遭難したパーティが事故当日にたどった栂池ヒュッテから白馬山荘までの行程上には、エスケープできるルートや山小屋はまったくない(白馬大池山荘は営業期間外)。しかもいったん主稜線に上がってしまったら最後、白馬山荘までは風雪を避けられるような場所も皆無といっていい(風下側に逃げようとしても滑落してしまう危険がある)。だとしたら、すでに天候が荒れはじめていたと思われる主稜線に上がった時点で、引き返すという判断を下せなかったのだろうか。穂高連峰でのケースでも、北穂高小屋に着いたときに予定を変更して停滞するという選択肢をなぜ選べなかったのか。
この2つのパーティはどちらも6人メンバーで、九州からやってきているという点も共通している。6年前(2006年)の10月には、やはり九州から来たガイド登山の一行7人が祖母谷温泉から白馬岳へ向かう途中で悪天候につかまり、4人が低体温症で亡くなるという同様の事故も起きている。これらの事例から想起されるのは、遠方から来ていることが計画の強行につながっていなかったか、そして6、7人という人数が悪天候下でのスピードダウンをもたらさなかったか(ほかの登山者の目撃談や救助要請した時間などから考えると、両パーティの行動ペースは明らかに遅い)、という疑問だ。それらが判断ミスの一因となった可能性は否定できない。
今回の白馬岳と穂高連峰のパーティのメンバーは、決して初心者というわけでなく、経験の長い山慣れた人が多かったという。両パーティとも事前に登山計画書を提出しており、白馬岳のパーティの場合は所要時間を標準コースタイムの1・5倍で計算してあったそうだ。そうしたことを考えると、当然、豊富な経験に基づき、さまざまな判断材料を考慮して決行を決めたのだと思うが、いずれにしても結果的にどこかで間違った判断を下してしまったと言わざるを得ない。
もちろん、同じ日に同じコースをたどった登山者はほかにもいる。そのなかのあるパーティは途中で引き返してきて難を逃れ、またあるパーティはなんとか無事に歩き通している。彼らと、遭難したパーティとの差はどこにあるのか。それを詳しく検証することができれば、より明確な教訓が得られるはずである。
ところで今回の白馬岳での遭難をめぐる報道では、関係者の当初の発言として、遭難者が全員軽装だったことが大きく報道された。曰く、「Tシャツの上に夏用の雨がっぱを着ただけの軽装備だった」「6人とも防寒用のダウンやフリースを身に着けていなかった」「この時期、冬山装備が常識の北アルプス登山では考えられない軽装」などなど。
しかし、長野県警が最終的に確認したところによると、後日回収されたザックの中にはダウンジャケットなどの防寒具は使われないまま入っていたというが、6人のなかにはダウンジャケットを着ていた人が2人いたし、最新のレイヤードを取り入れ上半身のウェアだけで7枚重ね着していた人もいた。いちばん薄着だった人でさえ、半袖と長袖のシャツにアウターのジャケットを着ていたのだ。春山で行動するウェアとしては決して軽装ではないし、現場では使用した形跡のあるツエルトが発見されるなど、悪天候に対処しようとした工夫も見られる。
それがなぜ「薄着だった」ということになってしまったのか、理解に苦しむ。間違った情報は多くの人に誤解を招き、遭難者やその家族にいわれなき誹謗中傷が浴びせられることになる。自戒を込め、関係者やマスコミは正確な事実を発表・報道すべきである。
ただ、爺ヶ岳で遭難した女性については、装備および計画が不充分だったようだ。扇沢の登山指導所で女性に対応した北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会理事の矢口正人は、「どちらへ行かれますか」という質問に対し「五竜まで」という答えが返ってきてびっくりしたという。
「この日だけで爺ヶ岳登山口から四十数人の登山者が入山しましたが、全員が鹿島槍ヶ岳の往復するという計画でした。この時期、扇沢から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳を越えて五竜岳まで行けるのは、ごく限られたエキスパートの登山者だけです。なのにその女性はスパッツもせず、ピッケルも持っていませんでした。一見して素人のような恰好でしたね。しかもザックは30リットルぐらいの小さなもので、そのザックからストックを取り出していたようでした」
女性は矢口氏の説明や問いかけにも終始無言で、「鹿島槍へのピストンに変更したほうがいいですよ」というアドバイスに従って登山届けに記入はしたが、矢口氏がほかの登山者の応対をしているうちにいなくなってしまったという。ちなみに自作の登山計画書(登山届け)は持っておらず、冷池山荘にも予約の連絡は入っていなかった(当日、冷池山荘には約35人の登山者が宿泊したが、そのほとんどが事前に予約を入れていた)。
報道によると、この女性は登山歴約15年で、毎週のように山に出掛けており、今年の1月にはキリマンジャロにも登頂しているという。それほど山の経験があるのに、なぜ無謀としか思えない山行を実施しようとしたのか。その疑問は解消されないままである。
なお、白馬岳で遭難したパーティについては、なぜひとかたまりになって亡くなっていたのかという疑問も残る。登山中に悪天候に遭遇して低体温症になる場合、パーティのメンバー全員が同じタイミングで同じように動けなくなることはまず考えられない。いちばん先に病状が進行した者がまず行動不能になり、まだ動ける者は救助を求めるための行動を起こすというのが、これまでの事例で見られたパターンだ。前述の6年前のガイド登山の遭難や、3年前のトムラウシ山でのツアー登山の遭難では、力尽きた順に倒れていったので、結果的にパーティはバラバラになっている。
それがこのケースに限っては、なぜバラバラにならなかったのか。いちばん最初に倒れたメンバーを介抱しようとしているうちに、全員がその場で低体温症になってしまったのか。あるいは6人が寄り添って猛吹雪をやりすごそうとしたのか。その謎も残念ながら明かされることはないだろう。
最後になりましたが、亡くなった方々のご冥福をお祈りするとともに、同様の事故が繰り返されないことを願っています。